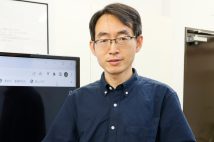デザインのユニークさでも知られる「舞洲スラッジセンター」
「大阪オリンピック」の夢の跡
夢洲に投入されるのは、下水汚泥を燃やしたもの。焼却は、夢洲に「夢舞大橋(ゆめまいおおはし)」でつながっている舞洲の壮麗な施設で行われる。
この「舞洲スラッジセンター」は、汚泥を焼却する施設の中で、世界的にみて最も芸術的な建築物の一つなのではないか。ウンコを燃やすためだけの施設ながら、約900億円の総工費がかかっている。
なぜそんな巨費を投じてド派手な焼却場を造ったか。背景には、幻に終わった「大阪オリンピック構想」があった。
大阪府や大阪市が、2008年の夏季オリンピックの招致を目指していたのである。〈世界初の海上オリンピック〉を目論んで、開催候補地に舞洲を、選手村に夢洲を想定していた。2001年に開催地は北京と決まったが、舞洲スラッジセンターはすでに着工済みだったのだ。
デザインのユニークさでも知られる「舞洲スラッジセンター」
臭いものに蓋 「迷惑施設」の悲哀
2004年にこの施設が稼働するまで、大阪市は下水汚泥を脱水して粘土状の脱水汚泥にした後、800~900度で焼いて灰にし、埋め立て処分をしていた。
対して舞洲スラッジセンターは、1200~1400度で焼く。すると、脱水汚泥がドロドロに溶ける。それを水で急速に冷却すると、粒子の細かい砂状の「溶融スラグ」になる。溶融スラグはガラス質の固形物で、黒くキラキラしていて、黒曜石やガラスの破片に似ている。
〈溶融スラグは建設資材等に利用できるので、埋め立てが不要になります〉
センターのパンフレットで同市建設局はこううたっている。灰にすると脱水ケーキの8分の1までしか容積が減らないが、溶融スラグなら15分の1になる。かさが減ってなおかつ資源を有効利用できる、一石二鳥の施設というわけだ。
舞洲スラッジセンターが建つ前、大阪市の焼却炉は他の自治体と同様、建物で覆われていなかった。
「昭和50年代ごろから焼却炉を整備したときは、むき出しの形だったんです。その後、 溶融炉を採用してスラッジセンターを建設するにあたり、臭気や騒音への対策の観点から、すべて建物の中に収める形にしています」
大阪市建設局下水道部調整課の澤田考正さんがこう解説する。建設局は咲洲のアジア太平洋トレードセンターに入居している。毎朝ここから、作業員を満載したバスが夢洲へと発車するのだ。
むき出しの焼却炉を使っていたころは、下水処理場からダンプカーで下水汚泥を運んでいた。それもあって悪臭や騒音、振動への苦情が出ていた。そこで炉を建物に格納し、下水汚泥は地中のパイプで送ることにして、悪臭と騒音の問題を解決した。
臭いものに蓋とばかり、汚物を見えなくし、におわなくさせることが優先された。引き換えになったのが、排熱である。
「基本的には空間を区切って、それぞれ局所的に換気を行う形です。ただ、温度はかなり高い状態になるんですけども」(澤田さん)
換気や冷却、断熱を組み合わせ、極力室温が上がらない対策を取っている。
「作業員の労働環境を守るために、基本的には40度くらいで管理を行うことにしています。炉の本体の近くは、どうしても非常に温度が上がるんですけども、そういうところは点検をする箇所を局所換気するなどの対応をしています」
市民から臭い、うるさいと嫌がられる迷惑施設。それをおとぎ話のような見た目の華麗 なパッケージで覆い、外界と遮断する。
建築は、さまざまな矛盾を拡大させながらも、今後も使い続けられる見込みだ。パッケージに包まれた目立たぬ主役である溶融炉の方は、老朽化で近く使命を終える。
エコロジーを掲げ、経済成長と環境保護の両立を夢見た、一つの時代の抜け殻。そういうものに今後、このスラッジセンターはなっていくのだろう。
(第3回を読む)
【著者プロフィール】
山口亮子(やまぐち りょうこ)/ジャーナリスト。愛媛県出身。2010年京都大学文学部卒業。2013年中国・北京大学歴史学系大学院修了。時事通信社を経てフリーになり、農業や中国について執筆。著書に『日本一の農業県はどこか―農業の通信簿―』、共著に『誰が農業を殺すのか』(共に新潮社)、『人口減少時代の農業と食』(筑摩書房)などがある。雑誌や広告の企画編集やコンサルティングなどを手がける株式会社ウロ代表取締役。