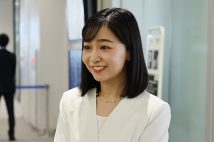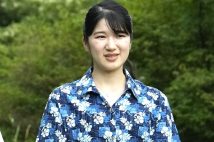2024年の都知事選では、ライバル候補同士だった清水国明氏(左)と安野貴博氏(右)が合同演説会を開催(2024年6月写真撮影:小川裕夫)
例えば、安野氏は都知事選でタレントの清水国明候補と2人で合同演説会を実施している。2人の候補者が仲よく並んで街頭演説をする光景は、なかなか見ることができない。なぜなら、安野氏と清水氏は互いに票を取り合うライバルなのだから、合同演説会は相手を利する行為になりかねない。しかし、安野・清水両氏はそうした敵対関係を超えて選挙で協力する関係を築いた。
今回の参院選だけに限った話ではないが、最近の選挙戦は分断を煽るような言説が支持を集めやすい。安野氏は都知事選の当時から「選挙は相手を打ちのめす戦いではない」と口にし、参院選でも「(チームみらいは)分断を煽らない。あくまでも政策の提案で勝負する」と繰り返した。
あくまでも自分たちの政策を語ることで有権者からの支持を拡大する。安野氏の選挙戦は理想的ではあるが、逆説的に言えば非現実的でもある。選挙は政策競争であると同時に権力闘争という側面も持っている。
どんなに政策が優れていても広く支持を集めなければ議員にはなれない。一票を入れてもらうには、力強い発言を求められ、そうした力強い発言が有権者を熱狂させる。議員になれなければ、どんな素晴らしい政策であっても、実現することはできない。
なにより、有権者の考え方は十人十色。誰もが賛同できる政策はなく、ゆえに「政治(家)に100点満点はない」とも言われる。
それらを鑑みれば、淡々と政策を提案する安野氏およびチームみらいの選挙スタイルは時代に適しているとは言い難い。ましてチームみらいは国政初挑戦で、擁立した候補者たちの顔ぶれを見ても国会議員や地方議員の経験者は見当たらない。わずかに総務省や厚生労働省の職員経験者がいるぐらいで、選挙に通じていると思われる人物は不在だった。いわば、チームみらいは選挙の素人集団で、そうした部分に危うさを感じることはあった。
また、テクノロジーのプロ集団であることを強みにしていたが、それらに傾斜しすぎてテクノロジーでは到達できない”人の心”の部分をケアできていないという不安を感じた。また、全候補者がテクノロジーを強調するがゆえに、党首の安野氏を除けば候補者たちの”顔”が見えないことも一票をためらうマイナス要因になるかもしれないと思われた。政治はロジック(論理)よりもエモーション(感情)で動くことが多い。それは、今回の参院選でも証明されている。
しかし、安野氏が率いるチームみらいは筆者が抱いた懸念を跳ね返した。前述したように、都知事選の得票を見れば本人が当選することは決して非現実的ではなかったが、今回はそれ以上に支援の輪を広げ、得票率も2パーセントを超えて政党要件もクリアした。これによって、チームみらいは正式な政党となり、政党助成金が支給される。
本来、政党助成金は所属議員の政治活動や選挙活動、党運営の資金として使われる。チームみらいは政党助成金をそうしたことに使わず、政治を変えていくためのテクノロジー開発費用に充てると宣言している。そうした部分も、旧来の政党とスタンスが異なる。