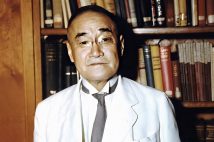ソロモン海を航行する日本軍の輸送船。敵機の空襲に犠牲も大きかった(提供)
空襲がないときは農園づくり
昭和18年9月以降、ブーゲンビル島への補給はまったく絶え、食糧事情は日に日に悪くなっていった。支給されるのは僅かな米と乾燥野菜だけ。昭和19年中頃にはその米も底をつく。栄養失調にマラリアが追い打ちをかけ、兵員の体力は衰えるばかりだった。
対空戦闘には機敏な動きが要求されるが、隊員たちは皆痩せこけて、立っているだけで精いっぱい。高角砲の弾薬筒を取り落としたり、砲手の力が足りず、弾丸がスムーズに薬室に入らなかったりすることもあった。
「やむなく、各隊ごとに、戦いながらジャングルを切り開いて農地を開墾し、自給自足の態勢を整えることになりましたが、開墾するまでが大変な労力なんです。空襲がないときはもっぱら農園づくりに励みましたが、戦闘や訓練で時間が取られる上に病人が多く、なかなかはかどらなかった。イモが生育するまではイモの葉を煮て、わずかに飢えをしのいでいました」
福山隊では、漁師出身者で漁労班を編成して、魚とりやフカ(鮫)釣りに派遣した。塩も不足したので、製塩班をつくり、海岸でドラム缶を使い、海水を煮て塩を得たが、燃料となる薪を用意するだけでも、衰えた体には重労働だった。食糧不足は各隊とも同じだったので、畑荒らしが頻発、ときに発砲騒ぎや自殺者が出ることもあった。食糧を求めてあてどもなく歩き回る兵の姿を見ることもめずらしくなかった。
100名の部隊で4ヘクタールの畑があれば、生きてゆくために十分なイモと少々の野菜をつくることができる。福山隊では8ヘクタールの畑を耕し、パイナップルやインゲン豆も栽培していた。
昭和19年秋頃にはイモの生育もよくなり、しだいに食糧事情は好転してきたが、こんどは医薬品が不足し、マラリアで病死する者が増えてきた。しまいには、医務隊から食糧と引き換えに流出した薬にも闇値がつき、マラリア薬1粒が10円もの値段(現在の2~3万円に相当する)で取引されるようになった。
「戦闘を主任務とする軍隊が、生きるためとはいえイモ作りに追われているのは異常な姿で、これではまるで屯田兵、あるいは集団入植です。こんな軍隊は、おそらく世界史上にないでしょう」