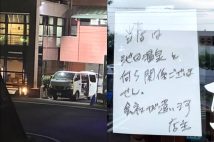部活の思い出を形にしたかった(イメージ写真)
関西の某公立高校教諭は、クラスの生徒が、まもなく引退する、所属部活の先輩の為に映像を制作していることを知り、応援していた。休み時間などを使って先輩の映像を撮影したり、後輩のメッセージを集めたりと精力的に動き、ついに映像は完成した。だが、その映像が公開されることはなかったという。
「ある先輩の親が、なぜ無断で子供の映像を撮影したのか、その映像は誰にどこで見せるのか、そう問い合わせてこられたんです。子供のやっていることだし、教員は見守るのが当然とお話ししましたが、何かあったら、例えば写真や映像が怪しげなコトに使われたら、どう責任をとるのかと詰め寄られました」(公立高校教諭)
生徒の親が不安視していたのは、近年、他人の卒業アルバムなどの写真を用いた「ディープフェイク被害」が、学校などで相次いでいることであった。教諭も、そうした問題があることはテレビ報道などで知っていたが、まさか自分の身近でそうした話題が出るのかと、信じられなかった。
「それをきっかけに、他の親御さんや教員からも、ネットにあげるのは駄目、写真や動画を撮るときは、子供本人だけでなく親の承諾も必要、といった声が上がり、収拾がつかなくなって計画は経ち消えました。計画した生徒たちには本当に申し訳ないというか、どうにか教員たちが後押しできなかったかと悔しい思いです。それから、例えば運動会はどうか、合唱コンクールは撮影はダメだが録音はいいなど、議論が拡大していきました。非常にやりにくい、というのが本音です」(公立高校教諭)
写真や映像を撮影すること、閲覧したり共有したりすることも、かつてと比べれば格段に安価で簡単に行えるようになった。手軽すぎるゆえに、悪意ある第三者による不本意な利用も発生する可能性が大きくなる。似たようなトラブルは今後も起きるはずだが、子供を守りたいという親心を何よりも尊重すべきなのか、大人が抱く不安の為に子供の行動を管理制限することを自重すべきなのか。親たち、教員たちの葛藤は続く。