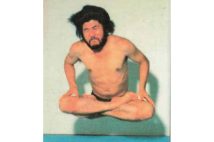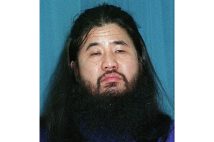「人を叩いてなんぼ、という人生に流された記者は、私を含めて容易に天国には行けない、と思うんですよ。」
今回の本の帯に「恥辱に満ちた半生」ってあるけど、僕もいろんなことがあったから、本当は自分を外し純粋なルポを書きたかった。でも、編集者は、「地方では何を生きがいにやってきたのか」、「特ダネを巡って上司とぶつからなかったのか」、「忖度を求められなかったのか」、「渡邉恒雄主筆というドンといかにぶつかったのか」と絶えず聞かれ、人のことを書くなら自分のことも書け、とも言われたのです。
──それで当初の予定よりも長く、3年2カ月にわたる連載になってしまったのですね。
自分のことを書き始めると、途中でやめるわけにはいかなくなっちゃったんですよ。
渡邉主筆(故人、読売新聞グループ本社代表取締役)の話も書いているけど、僕は巨人軍の球団代表を務めながら、月刊誌や野球雑誌に記事やコラムを書いていたんです。書き続けることは自分の道だし、球団の宣伝や信頼につながると思っていた。経営の端くれにいても、一度記者を志した者はずっと書くべきだと思っています。育成選手制度がうまくいっているころは渡邉主筆も認めていたのに、チームが不振になると、このコラムをやめろという話があった。それは書き手に戻る道の途中で起きたことだけど、そのころになって「面白い」と読者の評判になって、ドンとの対立や結末まできちんと書かざるを得なくなった。連載が長くなった一因です。
旧統一教会の報道で有名になったジャーナリストの鈴木エイトさんの話がこの本に少し出てくるんだけど、もっとあの人の話を詳しく載せるとか、秋田魁新聞のイージス・アショア配備を巡る特報など、地方紙などの記者の話をもっともっと入れたかった。
──「記者出身ならずっと書くべき」というお話をもう少し教えてもらえますか。
僕が入社したころ、先輩から言われたのは、お前はハンターになりたいのか、ライターになりたいのかってことなんです。
──ライターは文筆家という意味でしょうけど、ハンターはどういう意味ですか?
ハンターというのは、ツルハシを持って鉱脈を探す鉱夫みたいな、堀り屋だと思っているんですよ。隠された事実を発掘する、発掘者です。僕はそういうハンターでありたいって思っていたんです。ライターというのは、コラムニストとか論説委員、そういう筆の技巧や見立てで食っていく人ですよ。だけど、今はこの二つに加えて、マネージャー、つまり経営とか管理部門に携わる第三の道を目指す人もいるんですね。
──今は、新聞社に入って早い時期からマネージャーを目指す人がいるということですか?
そうですね。読売も編集局と、社長室など管理部門をジグザグに渡って偉くなる人が増えました。僕は残念なことだと思うんだよね。だって、新聞社の幹部になりたくて記者職を目指したのですか。特ダネ記者になりたいとか、論説委員、コラムニストになりたいというならわかるけど。でも、今はそういう人もいるんですよね。この本の中にも書いたけど、最初から「僕は社長になります」と宣言した渡邉さんみたいな人もいるし。
──記者である以上、ハンターやライターを目指すべきということでしょうか。