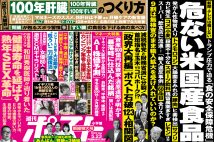再建中の「獺祭ストア」の前で話す桜井一宏社長(撮影/武美静香)
1階と地下の機械室は水浸しになり、排水システムはダウン。西田さんらは必死に建物内の泥や水をスコップでかき出した。東京出張から慌てて戻った桜井一宏社長(42才)も茫然とした。
「昔からこの辺りは大きな災害もなく、自然が美しく平和でした。川は澄んでいて魚も捕れました。小さい頃から川遊びをしていた東川が濁って無残に氾濫するなんて、思ってもみませんでした」
幹部社員が集まるとすぐさま本社2階で会議が開かれた。クーラーが止まった室内で全員が汗だくになるなか、一宏社長はこう檄を飛ばした。
「壊れたものは直す。汚れたものは洗えばいい。起きたことをくよくよせず、まずチャレンジしてみよう!」
酒造にとって死活的な問題となったのは停電だ。年間を通じて酒造りをする旭酒造は、本社7~9階の発酵室に発酵中の酒を大量に保存する。この部屋は品質管理のため、常に5℃を維持する必要がある。
「いわば大きな冷蔵庫の中で酒造りをしているのですが、豪雨で送電線が切断され停電し、発酵中の150本・50万リットルものタンクの温度がコントロールできなくなりました。非常用電気をかき集めても足りず、危機感が募りました」(一宏社長)
空調の効かない部屋は、発酵中に排出される炭酸ガスが充満し、危険極まりない。社長らは息を止め、駆け足で室内を巡った。社長の父、博志会長(68才)も、事態の深刻さを痛感していた。
「電気がひと月止まると、発酵中の獺祭を含めて製造過程の酒が全滅し、概算で40億円の損失になる。これは年間売り上げの3分の1。この状態が3か月続けば会社が潰れてもおかしくない」(博志会長)
中国電力から「回復までに3か月はかかる」との見通しを伝えられると、社内全体が重い空気に包まれた。誰もがついつい下を向き、口数も減っていた。そんな破滅的状況のなか、旭酒造に救いの手を差し伸べたのは、地元の人たちだった。
「長くつきあいのあった地元の建設会社の担当者が山口県内のあちこちから自家発電装置を集めてくれて、そのお陰でなんとか最低限の電力維持ができました。いくら感謝してもしきれません」(博志会長)
まさに九死に一生。丹精込めて造り上げた酒が、周囲の尽力で壊滅を免れた。結果、3日間の停電で済んだのだ。しかし、話はそこから始まる。肝心の味がどうなっているのか。商品として遜色ないのか──。
発酵室で味をチェックするとき、皆の表情は硬かった。味はたしかに充分おいしかった。しかし、一宏社長は非情な決断を下す。
「味はいつもの獺祭とほぼ変わりませんが、私たちの考える厳しい品質基準には達しませんでした。ここで妥協してはいけない。一升瓶換算で約30万本分は、獺祭ブランドとして認められないと判断しました」(一宏社長)