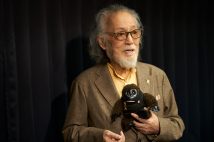地図で地形を確認し、見終えた場所を1か所1か所、塗りつぶしていく
オフィス街や工場地帯では倉庫や資材置き場、建物と建物の間の狭い空間、コンテナの下などがチェックポイントとなる。各所の許可を得て、入念に捜索する。
その後、住宅街へと向かい、ペットレスキュースタッフのみでの捜索となった。建ち並ぶ家々。この地域には蔵や納屋なども多い。そのぶん、縁の下や納屋の中など、隠れ場所も多い。藤原さんと飯塚さんは身をかがめ、懐中電灯で光を当てて確認していく。
ウッドデッキの下やメーターボックスの裏や中も猫が隠れやすい場所となる。マンションやアパートを捜索するのであれば、1階部分のベランダと地面の隙間なども発見の可能性が高い。特に、暗い場所は注意深く懐中電灯を照らして捜索するといい。天井や荷物の隙間など、納屋は猫が入り込みそうなスペースが多い。念入りに捜索する。
藤原さんは物置の下の10cmもない隙間にも光を当てる。それだけの空間があれば、猫は充分潜り込めるのだという。
「ここは跳び移れるなぁ」──藤原さんがポツリとつぶやく。
「あの崖からあの家の屋根までくらいなら、余裕で跳び移れます。猫は野性味の強い動物で、身体能力はズバ抜けているんです」
猫は自分の体長の5倍くらいは垂直跳びができるという。さらに、一軒一軒インターホンを鳴らし、敷地への立ち入り許可をもらう。なかには、「あー、モグちゃんね。まだ見つからないの?」と声をかけてくれる人もいる。配布したチラシの情報が行き渡っているのだ。
藤原さんと飯塚さんは軽い身のこなしで、物置や縁の下をのぞき込む。猫を驚かせないように物音や足音もできるだけたてないことも大切だ。
こうして捜索範囲を狭めながら、移動ルートを分析し、絞り込んでいく。その際には、紙の地図が欠かせないという。
「猫の場合は狭い範囲を密に探すので、住宅地図がいちばん適しています。私が使っているのは1500分の1の縮尺で、建物名など詳細な情報が書かれたものです。捜索によって得た情報をそこに書き込み、俯瞰して眺め、範囲を絞り込んでいく。それにはスマホの地図アプリより、紙の地図の方が使いやすいのです」(藤原さん)