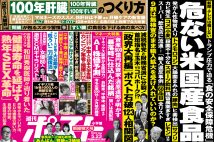新静岡駅近くの踏切を通過中のA3000形。A3000形の車体は7色のバリエーションがあり、shizuoka rainbow trainsと呼ばれている(撮影:小川裕夫)
約半世紀ぶりの新車両も中古ではなく新造
先述したように、当時は最先端とされた1000形も歳月とともに老朽化したため、2016年からA3000形という新型車両が登場した。A3000形も昔の静鉄車両の規格と電圧を踏襲している。規格と電圧は踏襲しているが、当然ながらA3000形の性能そのものは向上している。また、sustinaと呼ばれる新開発された軽量ステンレス車両となった。そして、驚くべきことに、A3000形も中古ではなく新製車両となっている。
「他社から中古車両を買った場合、どんなに大事に使っても最長で20年しか持ちません。新製車両なら40年は持ちます。それだけだったら中古車両を購入して使うメリットもありますが、他社の車両は静鉄と規格も電圧も異なります。他社から安い中古車両を購入しても、静鉄で走るために改造しなければなりません。その改造費もかかりますし、異なった規格の車両を使うなら駅施設を改良しなければなりません。中古車両を購入した際に発生する費用と車両を新製した費用を勘案すると、新製の方が安上がりなんです。だから静鉄はA3000形を新製したのです」(同)
静鉄グループは、鉄道・バスといった交通事業を中心に経営を多角化している。その中でも、自動車販売業のシェアが大きい。そうした一側面を捉え、鉄道ファンからは「自動車販売で儲けているから、自社で車両を新製できる」と言われることがある。
そうした面があることは否定できないが、静鉄は自動車販売の売上にあぐらをかかず、独自の経営戦略で車両を新製してきた。
昨今、人口減少やマイカーの普及、さらにコロナ禍によって減少した観光客需要といった要因から地方鉄道の経営は厳しさを増している。静鉄も経営が順風満帆とは言い難い。
それでも静鉄は中古車両を購入することで費用を抑制するという、鉄道業界の既成概念を覆す経営戦略で新製車両を導入してきた。新製車両は静鉄の存在感を発揮することにもつながっている。
地方私鉄に逆風が吹く中、静鉄のような既成概念を打破する地方私鉄が次々と現れて、地方の鉄道が再生・活性化することを期待したい。
静鉄の顔としてデビュー50年を迎えた1000形。間もなく全車が引退する予定(撮影:小川裕夫)