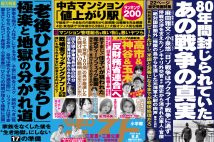トークで笑いをもたらす明石家さんま(番組公式Xより)
節目に頼らずトークで盛り上げる
そんなさんまさんは制作サイドにとって子ども、親、祖父母の3世代視聴を狙える貴重なMC。どのテレビ局も「家族そろって見てもらうことでリアルタイム視聴につなげたい」という狙いがあり、さんまさんは出演者だけでなく視聴者の世代もつなぐことも期待されています。
民放各局は2020年春に視聴率調査がリニューアルされて以降、最もスポンサーが求めるコア層(主に13~49歳)の個人視聴率獲得に向けた番組制作をしてきました。しかし、コア層の配信視聴が進んでリアルタイム視聴がますます減り、さらに最大のボリューム層である団塊ジュニア世代がすべて50代となりコア層から外れたことで戦略変更を決断。昨春から昨秋にかけて各局が「ターゲット層の上限を50代まで広げる」などの方針を発表していました。そのため中高年層からの支持が厚いさんまさんの重要度は再び上がっていると言っていいでしょう。
そしてもう1つ民放各局にとって重要なのは、さんまさんが改編期特番や年末年始特番などの大型企画で、お祭り騒ぎの明るいムードを作れること。宴会部長のようなポジションから率先してハイテンションで盛り上げるタイプのMCは中堅や若手を含めても見当たらず、「けっきょく毎年さんまさんに頼る」というパターンが続いています。
また、昨年の出演番組でさんまさんの再評価につながったのが、“節目”における対応。さんまさんは昨年、芸能生活50周年を迎えましたが、それを番組内の企画で生かすことはほとんどありませんでした。同様に今回の70歳を記念した特番も、それを生かした構成・演出は最小限に留めたという感があります。「○周年」「○歳」という節目を使って稼ごうとするタレントが多い中、それに頼らずトークで盛り上げるというスタンスを採ったことで、あらためて凄さがわかるのではないでしょうか。
「さんま限界説」もどこ吹く風
昨年の夏から秋にかけて「声が出ていない」「何を言っているのか聞き取れない」などと指摘した“さんま限界説”も報じられましたが、今年に入るといつの間にか消えていました。さらに、年末に出演した特番では、その声が枯れていることや引退をネタにするなど笑いに変えたことで、結果的に悪意のある記事を封じ込めた感があったのです。
さらに覚えている人は少ないかもしれませんが、2000年代、2010年代にも何度か“さんま限界説”が報じられました。しかし、さんまさんは意に介さず通常運行のみで対応。日ごろ「人に腹が立つということがない」と語っているように“お笑い怪獣”のイメージとは真逆の泰然自若のスタンスで限界説を覆してきたのです。
民放各局にとって今なお視聴者層として貴重な中高年の視聴者にとってさんまさんは元気をもらえる存在であり、「そろそろ引退してもいいのでは」などと思っている人は少ないでしょう。さんまさんが望むかはさておき、70歳という節目に限らず、71歳、72歳、73歳と毎年の誕生日をともに祝うくらいの構成・演出のほうが視聴者を喜ばせられるのかもしれません。
【木村隆志】
コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい!会話術』など。