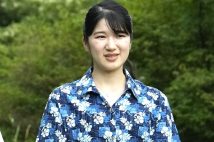若年層の自殺件数が増加傾向にある(厚生労働省「令和6年中における自殺の状況」)
座間事件がきっかけで始まったSNS相談
厚労省はこの事件を受けSNS上でのSOSがキャッチできていないとして、SNS相談の拡充をし、相談を担うNPOなどに補助金を出すことにした。NPOや数ある支援者よりも、白石のような犯罪者のほうが、自殺願望のある若年層の心を明らかにつかんでいた。子どもたちのSOSは、SNSの見知らぬ人とのやりとりの中にあることがわかった厚労省は、LINEなどを窓口とするSNS相談に目をつけた。筆者も、SNS相談を始める複数のNPOで、相談員の研修を目的とした講演をしたことがある。
また、厚労省は「SNS等における自殺に関する不適切な書き込みへの対策」として、自殺の誘引情報などの書き込みを禁止し、ユーザーへの注意喚起をした。さらに、自殺誘引情報の削除を強化した。つまり、事件以降、インターネットに書き込まれる「死にたい」などのSOSを、SNSなどの相談に吸収しようというものだった。
たしかに、SNS相談に寄せられる相談は増えた。2019年4月~2020年3月までは4万5106件(このうち「自殺念慮」は1万3508件)、2020年4月~2021年3月は6万3028件(このうち「自殺念慮」は2万1324件)、2021年4月~2022年3月までは25万9814件(このうち、「自殺念慮」は14万7814件)と増加傾向だ。最新は2023年4月~2024年3月までで、27万1727件(このうち「自殺念慮」は14万582件)となっている。
もちろん、浸透度や相談体制が違うために単純な比較はできないものの、相談を寄せるユーザーは増えている。しかし、この間、若年層の自殺者数は減ることはなかった。つまりは、社会的には、SOSを発信し、SNSで相談を受け止めること自体が、自殺者数をストレートに減らすことにはならないことを示した。
子どもの自殺を減らすことは、既存の統計やデータをベースにした施策ではできない。同時に、既存の施策の中で提言や政策実行をしてきたプレイヤー(有識者など)では、限界があることを示している。
大きく転換するにはプレイヤーを変えて、あるいは加えて、新たな視点で政策に取り組む必要がある。本来は、そのための「こども庁」であり、「子どもの自殺対策室」のはずだったが、いまだに、古い施策やプレイヤーの枠組みを超えていないように思える。
インターネット相談は子どもの自殺防止に役立つのか
厚生労働省はこの座間男女9人殺害事件を受けて、LINE相談を民間団体に委託する事業を始めた。しかし、LINE相談が始まっても、10代の自殺者数は減少していない。むしろ、増加している。SNSを含む、インターネットを介した相談は、どんな変化をもたらしているのかは、厚生労働省として検証していない。