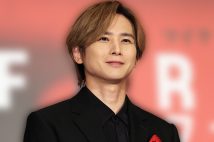【立川談志】橘氏は楽屋で聞いた談志の言葉の中で「俺は落語家やってんじゃねえ。落語使って立川談志やってんだ」という一言が心に残っている。写真集では〈談志という宇宙〉と評した
最近の「落語ブーム」と違い、まだ寄席に閑古鳥が鳴いていた1995年から楽屋や舞台袖で芸人たちを撮り続けてきた演芸写真家の橘蓮二氏。橘氏が見た名人たちの姿を、ノンフィクションライターの中村計氏が訊いた。【前後編の後編。前編を読む】
理想は「撮らないように撮る」こと
橘が演芸の世界を本格的に撮り始めた頃は、何より立川談志と柳家小三治が最後の輝きを見せていたときでもある。
「談志師匠も小三治師匠も、まだ、めちゃめちゃ怖かった頃です。とにかく近寄りがたかった。でも、それがまたカッコよかったんですよね」
談志は最初の2年間、まったく口をきいてくれなかった。
「『おはようございます』とあいさつしてもほぼ無視でしたね。それがあるとき、初めて名前を呼んでくれて。『橘っ!』と。もうびっくりして。『もう、おまえ、好きに撮っていいぞ』って。嬉しかったですね」
談志の忘れられない高座がある。2007年12月18日のよみうりホールだった。談志は年末の独演会で『芝浜』をかけるのが常だった。しかし、ガンに体を蝕まれ、体調は万全ではなかった。ところが途中から登場人物たちに命が吹き込まれたかのように躍動し始める。橘が回想する。
「最初は声が出ていなかったんです。でも中盤から神様が乗り移ったかのようでした」
ただし、その伝説の高座の瞬間を、橘はほとんどフィルムに焼き付けることができなかった。
「あの頃はフィルムカメラでしたから。どんなに消音カバーで厚く覆ってもシャッター音はするので、もう撮ることは不可能だと思っていました。お客さんたちも咳払い一つできないような雰囲気でしたし。演芸写真家にとっていちばん大事なのは無理してまで撮らない、ってことなんですよ。その日の高座だけで終わりじゃないんで。演者さんの気持ちを万が一でも削りかねない行動は慎まなければいけないんです」
かすかな音でさえ立てられないときは靴を脱ぎ、靴下を二重にする。咳が出そうなときはマスクを二枚重ねてかけ、のど飴を携帯しておく。また、持っている服はいつの間にか黒ばかりになった。
「たとえば白いシャツを着て袖にいたら、動いたとき、演者さんが気になるかもしれないじゃないですか。色で悩まなくていいので、服を買うとき楽になりましたよ」
大人気番組『笑点』の司会者で、城好きな春風亭昇太には、こんな風に言われたことがある。
「橘君、戦国時代だったらいい忍者になれるよ」
橘の理想は「撮らないように撮る」ことだ。最高の褒め言葉だった。