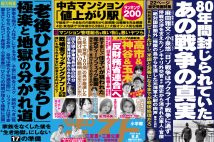被告人は心菜さんと心中しようと計画した(画像はイメージ、Getty)
「介護疲れではない」
検察官からも質問をする。犯行による結果は検察官として当然追及しなければならない。ただ他の裁判に比べて、検察官の質問は言葉選びに配慮を感じた。
心菜さんは肺炎などの命の危機から何度も脱し、被告人や夫は「心菜は生きたいと思っている」と感じていた。新薬の影響で、「コミュニケーションを取れそうになっている」と感じることもあった。
事件前でも、その気持ちに変化はなかった。「20歳くらいまで生きて欲しい」と思っていたことも語った。
事件時には「親族にとって、自分と心菜はいない方がいいのでは」という心境に陥っていたと主張する被告人。しかし親族からの心ない言動は以前からあった。以前にも同様の気持ちになったことはないかと聞かれると、「ない」と即座に答える。
その理由として、娘には1日でも長く生きて欲しいという気持ちが時を経るごとに勝ってきた点。そして、傷つけられた親族とは縁を切ろうと思ったこともあるが、義母は日常的な生活を気遣ってくれており、実父も不妊治療の費用を捻出するなどの思いやりを感じたことを忘れることはできなかったという。ただ、肝心なところの気持ちはすれ違ったままであった。
家族への遺書は、睡眠薬を飲み始めてから思いついて書いた。理由は「娘の介護疲れと思われたくない」と述べ、検察官が様々な聞き方で「介護疲れ」と引き出そうとするものの、「自身の心の傷を対処できなかった自分の弱さ」と一貫した。
検察官は後に行われた論告において、「衝動的な意思決定」「短絡的な犯行」「他の介護殺人とは一線を画している」と指摘するなど、被告人が介護疲れを否定したことは、結果的に被告人にとって不利な主張になったと思われる。しかし一方で、心菜さんに真に向き合い続けてきた思いを感じる一貫さでもあった。