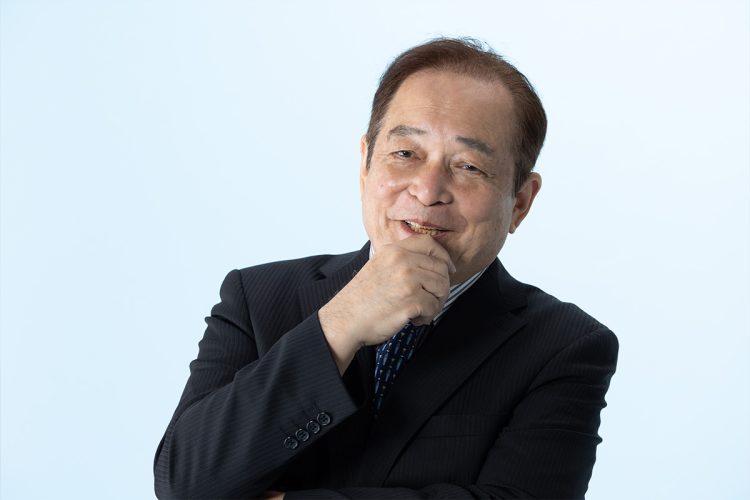清武英利氏がノンフィクション作品『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋刊)を上梓した
読売新聞社会部の記者、巨人軍代表を経て作家に転身した清武英利氏が、今年8月に、ノンフィクション作品『記者は天国に行けない』(文藝春秋刊)を上梓。自身を含めたさまざまな記者の特ダネに挑む矜持を描いた。今回、そこから欠け離れた記者たちへ厳しい意見を語る。【前後編の後編。「君は長い物に巻かれなかったか」と問うた前編を読む】
* * *
──前回は、記者は出世しても歳を取っても書き続けなきゃダメなんだというお話でした。
記者でいながら、取材相手の秘密を棺桶まで持っていくという人がいるじゃないですか、政治部や捜査幹部を取材した社会部なんか多いのではないですか。それは読者を裏切っていますよ。親しくなった政財界の大物、検察、警察首脳に対して、「きょうは遺書をいただきにまいりました」と言えるくらいの根性を持たないとダメなんだと思います。もっと言うと、「あなたの公的な秘密は私が書きます。今までずっとお聞きしたことはすべて書きます」と言えるくらいの度胸があって、初めて読者の負託に応えたことになるのではないですか。新聞社の取材費を使い、ハイヤーも使って密着してきたのに秘事は書かないなんていうのは記者道にも反している。書かざる大記者が僕は大嫌いです。
──記者というより政界のプレーヤーになってしまう人がいますよね。
そう、政局を演出する一人になっている。元東京高検検事長の黒川弘務氏と新聞記者たちが賭け麻雀をしていて問題になったことがありましたよね。
──そうでしたね、記者も賭け麻雀をしていましたね。
一緒に麻雀をやっていたこと自体よりも、その記者たちが、何があったのか書かないことが大きな問題なんだと思う。
──たしかに、黒川氏の定年延長問題(※)にしたって、本人の証言は少なくとも公開されていないわけですが、その記者たちなら書けたんじゃないですかね。
まだ書く時間は残されている。もし書いたとして、それを裏切りというんだったら、平気で裏切って書きなさいってことですよ。それが記者なんだから。だって特権を与えられているわけじゃないですか。普通の人は黒川さんの面識を得る自体まずできないですよ。麻雀も新聞社の看板を背負ってやった取材の一環なんでしょう。まあ、テレビで情報の切り売りをしたりして生きていくっていう生き方もあるんだろうけど、例えば検察の実態、官邸との距離、癒着など、読者が求めることを書かないと、記者とは言えないですよ。
【※黒川弘務氏の定年延長問題…2020年1月31日、安倍晋三政権が東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年を延長したが、これが恣意的なものではないかと疑われた問題。検察庁法では、検事総長を除き、定年は63歳で黒川検事長は当時62歳。63歳の誕生日が近づいていた。安倍政権は検察庁法ではなく、国家公務員法の条文にある、退職により著しい支障が出る場合の特例を適用した。当時、「安倍政権に近い」とされた黒川氏を検事総長に据えたいがための措置ではないかと取り沙汰された。この後、前述の賭け麻雀問題が露呈し、同年5月に黒川氏は東京高検検事長を辞職した(肩書きや定年規定などはすべて当時のもの)】
──なるほど、記者は親しくなった取材相手を裏切ってでも書くべきということですね。この本の中には、取材相手の胸襟を開かせる方法が取り上げられています。若い記者が読めば、取材方法のヒントになりますね。