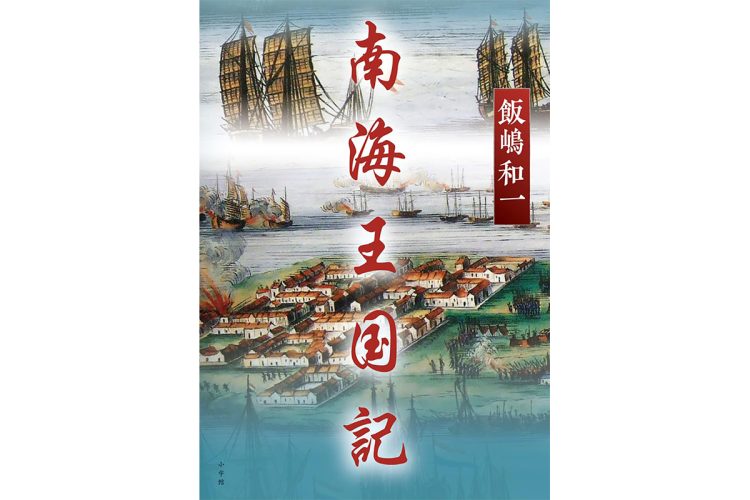『南海王国記』/小学館/2530円
【著者インタビュー】飯嶋和一さん/『南海王国記』/小学館/2530円
【本の内容】
約300年に及ぶ明王朝が滅亡し、清が正統王朝となった時期、鄭成功は「抗清復明」を掲げて戦い続ける。《天下こぞって信を失えば、誰もが人間である尊厳を棄て、人が人を食らうような亡天下が現出することになる。鄭成功の目の前にあるのは、まさしくそのとおりの世界だった》。その中にあって、孔子の言葉『古より皆死あり、民、信無くば立たず』を胸に、広く世界と貿易しながら台湾に国を建国した「海賊」の活躍を描いた1000枚の長編歴史小説。
明に対する思いというよりも、それしか拠り所がなかったのでは
寡作ながら、スケールの大きな歴史小説で、本好き、歴史好きに新作が待ち望まれている飯嶋和一さん。7年ぶりの新刊は、清朝の時代に、いまの台湾に独立国を打ちたてた、鄭成功の生涯を描く。
鄭成功は幼名田川福松。中国人の父、日本人の母のもと長崎・平戸に生まれ、かぞえ7つで父のいる中国・安海に渡る。科挙受験のためだったが、明が衰え清が勢力を伸ばすなか鄭成功も官僚になることをあきらめ戦乱に身を投じる。明の武将が次々、投降した後も抵抗を続けた。
近松門左衛門の浄瑠璃「国性爺合戦」に「和藤内」として登場するので、文楽や歌舞伎が好きな人なら名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれない。
飯嶋さんの小説は、人物の選び方、光の当て方が毎回独創的で、こんな人がいたのかという驚きがある。
なぜ今回、鄭成功が生きた時代を書くことにしたのだろう。
「長崎を舞台にした『黄金旅風』(2004年)を書いたときに海洋貿易に興味を持ちました。1600年代の半ばぐらいから、国姓爺船という奇妙な船が、とんでもない量の、中国から長崎に持ちこまれる生糸の7割ぐらいを運んでいる。それが鄭成功の船だったらしいというところから関心を持つようになりました。
中国の沿海だけでなく、ベトナムのあたりやタイ、フィリピンにも中国人街があり絹市場が形成されているわけです。日本も含めて行き来する、国ではないけどなにか生命体のようなネットワークが結ばれ、商取引が行われていたのが面白いと思いました」
かつて鹿児島の根占に行ったとき、フェリー乗り場の近くに「唐人町2丁目」という案内板を見たことがあるそうだ。近くの人もいわれを知らず、町史にも特に記載はなかった
が、「ここにもかつて中国人街があったんでしょう」と飯嶋さん。
鄭成功が台頭するのは、中国では漢民族の明が滅び、満州族の清が台頭する時期である。鄭成功の父芝龍も、師である銭謙益も清に降るが、鄭成功は、貿易で得た莫大な利益をつぎこみ、「抗清復明」を掲げて抵抗を続ける。
有力な武将たちが寝返り、清の髪型である弁髪にするなか、日本人の血をひいた鄭成功が、あくまで漢民族の王朝にこだわったのはどういう理由なのだろう。
「明に対する思いというよりも、それしか拠り所がなかったんじゃないですかね。鄭成功はもともとどこかに帰属している人ではありません。父の鄭芝龍は言ってみれば海賊の親分で、支配体制の外側にいた人です。
抵抗を続ける鄭成功は、清から見ると非常に厄介な存在で、資金源を断つため、住民を海岸沿いから移住させる『遷界令』というのを出します。海岸線の長さを考えると無謀な命令ですが、それぐらい脅威だったんだと思います」
台湾を支配していたオランダの軍を打ち破り、西洋の植民地支配を武力で終わらせたというのも驚きである。潮の満ち引きや季節風といった自然の条件を知りつくして海上で戦えるのが鄭成功軍の強みだった。
中国全土を支配した清も降伏させることはついにできなかった鄭成功だが、熱病の発作に悩まされるようになり、酒におぼれ、40歳になる前に台湾で病死する。
鄭成功亡きあとは、親族の主権争いや陰謀、誅殺といった明朝末期を思わせる内紛が一族の間に起こり、かつて鄭成功のもとにいた施琅の軍に滅ぼされてしまう。
国が存亡するかどうかの危機にも目先の利益や自らの出世のことしか考えられない人間の愚かさが、普遍的なものとして描かれる。
「どんな時代でも似たようなものというか、歴史の中で必ずそういうことは起きますね。人間の性っていうのかな。『いい加減、わかれよ』と言いたい気持ちにもなりますが、人間は変わらないですね」