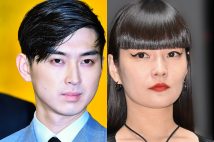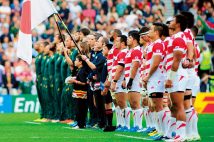ただ、一言だけ頑迷固陋な「白い巨塔」の歴史学界に、歴史の大原則をプレゼントしておこう。
「自浄作用の無い組織は必ず滅びる」である。
さて、ここ一連の記述のなかで、とくに用語問題に重点を置いて扱ってきたことの意義はおわかりだと思う。「大東亜戦争」を「アジア・太平洋戦争」などと言い換えさせることは、真の歴史の分析をする立場から見れば「百害あって一利無し」なのである。しかし日本の歴史学界、とくに近現代史の分野にはそれが正義だと誤解している人間が大勢いる。
その中核をなす左翼歴史学者は歴史における真実の探求よりも、帝国主義を糾弾するという左翼的正義の追求に重点を置いているからだ。それゆえ、すでに述べたように彼らの歴史記述は「公平な判決」では無く、「犯人の事情」や「情状酌量の余地」を無視し罪だけを強調する「検事調書」になってしまう。だからこそ彼らの研究や著作を引用するためには最大限の注意が必要なので、これは私に言わせれば近現代史を研究する場合の基本心得のようなものであり、それゆえ多くの紙幅を費やして語る必要があったということだ。
では、この問題を確認したところで「時系列」に戻ろう。
一九一九年(大正8)である。前年の十一月に人類最初の世界大戦である第一次世界大戦がようやく終わった。そして、
〈一月 パリ講和会議開催(日本側全権は西園寺公望、牧野伸顕ら)
二月 牧野伸顕、国際連盟規約に人種差別撤廃を盛り込むよう提案するが、オーストラリアの暗躍、アメリカ、イギリスの反対で否決される。〉
という流れがあった。
しかし、その「見返り」の形で四月から五月にかけて日本が熱望していた「中華民国山東省のドイツ利権の継承」が認められ、さらにドイツが支配していた赤道以北の太平洋の島々が、日本に対する国際連盟の委任統治領となった。事実上、日本の領土となったということだ。そして翌一九二〇年(大正9)に正式に発足した国際連盟において、日本はイギリス・フランス・イタリアと並んで常任理事国となった。アメリカはモンロー主義、ソビエトは共産主義の立場から連盟自体に参加せず(後にソビエトは加盟)、敗戦国ドイツは後に加盟したが、国家として安定を欠く中華民国は当初から加盟はしたものの常任理事国にはなれなかった。
つまり、この時点で日本、いや大日本帝国はドイツを抜いて欧米に伍する「列強」の一員になったのである。
(「ベルサイユ体制と国際連盟」編・完)
【プロフィール】
井沢元彦(いざわ・もとひこ)/作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。
※週刊ポスト2025年9月19・26日号