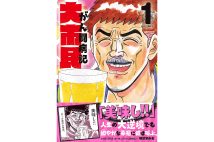何かと理屈っぽい架の父親はよく庭でゴミを燃やし、顰蹙を買っていた。ある朝彼の席には恭しく花が飾られ、いつもの嫌がらせだと架はうんざりする。が、そのうち〈自覚が足りない〉と高町までが言い出し、彼は自分が見ていなかったある現実を突き付けられる。
「世間で常識扱いされていることがあれば、その思いこみを利用するかたちで使ってみたりしましたが、どうやらそうやって読者を誘導するのがミステリーの手法らしいと、僕も編集者に言われて初めて知りました。
世の中の不条理や〈あまりにも残酷で気まぐれな不平等〉に若くして直面させられた人間がそこから抜け出そうとする話にしたのも、それが自分の一番気になることだからそうなったとしか言い様がない。実際は抜け出せないことも多く、ニュースを見る度に悲しくなるけれど、それでも彼らは生きてるんだぞということを描きたかったんだと思います」
実は家庭に事情を抱えた高町を救おうにも架はあまりに幼すぎ、手を差し出すこともできない。そのもどかしさや無力感を、十市氏は“幽霊”と呼ばれる少年の視点から丁寧に描き、大人と子供、虚と実といった境界線も全てが揺らいでいる。が、それほど不確かな足場の上に人は生きているのかもしれず、その中で架が高町を初めて〈友達〉だと思う気持ちだけが、絶対的で確かだった。
高町は言う、〈短いバトンは落とせない〉と。そして〈自分の状況で精一杯なときでも、案外まだ、ほかの誰かに同情できちゃったりするんだよね〉とも。詳しい意味は本編をお読みいただくとして、どんなに非力でも〈自分にできること〉を精一杯やろうとする友の言葉に背中を押されて架が踏み出す一歩に、我々大人が思うことは多い。
例えば〈自分が何者か〉という問題を大人が解決できているかというとそうでもないし、体は成長しても、中身はその局面局面で多少変わる程度。しかし、そのことが逆に救いになる場合だってあるのだ。
「僕が書きたいものは、基本的には犯人捜しにも謎解きにもこだわらず『読んでよかったと思ってもらえる小説』なんです」
リダクションとは一般に除去や修正を意味するが、本書に関する限り最も相応しい訳語は「再生」だろう。それも自らの手による再生を彼らはめざし、その隣に必要なのが友であり、信頼だった。
【著者プロフィール】十市社(とおちの・やしろ):1978年愛知県生まれ。中京大学卒。「就職活動はせず、地元でフリーターをしながら小説を書いています。作家になるためと言うより、自分が社会人になることにリアリティを持てなかったと言う方が、正確かもしれない(笑い)」。昨年Kindleダイレクト・パブリッシング(KDP)を通じて本作を個人出版。その才能に着目した東京創元社が「ミステリ・フロンティア」創刊10周年記念作品として本書を刊行、話題を呼ぶ。172cm、52kg、A型。
(構成/橋本紀子)
※週刊ポスト2014年5月30日号