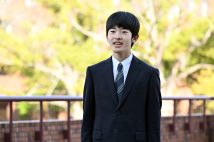中国・深センにあった日本企業の電子部品製造工場。三洋電機などは1980年代には6000人もの人を現地で雇用する規模の工場を合弁会社によって運営していた(イメージ、時事通信フォト)
「銀行から来た連中はコストカットが目的、よい物を作らなければいけないのに、よい物を作るなと言ってくる。とにかく金をかけずに、よい物でなくてもいいから売れるものを作れと。また営業は消費者の声ではなく大手家電量販チェーンの声を聞くようになりました。お金を調達するために銀行の言いなり、作ったものを置いてもらうために家電量販店のいいなり、それでうまくいくならともかく、ジリ貧になりました。コンサルも高い金をとって引っ掻き回すだけ、いよいよというときにはちゃっかり逃げてました」
もちろんそれだけが原因ではないかもしれない。時代の変遷もあるだろうし、そもそも会社の経営ミスも重なっただろう、しかし彼は納得できないと語る。
「元はと言えば出世した営業や事務方がよくわからない投資や多角経営を繰り返したあげくの経営難でしたから、それで最初に詰め腹を切らされるのが技術屋って、納得できるわけがありません。海外生産、資金調達も含めた合弁という名目で中国や韓国といった当時の途上国に技術提供もしました。私も実際、教えに行きましたよ」
隙間家電が多かったサムスンもLGも今や世界企業
思えば日本企業は高度成長期以降、韓国や中国に技術を提供し続けた。冷戦下の1970年代、韓国のサムスン電子は五流企業で簡易な半導体すらまともに作れず、LSIは不良品ばかりだった。
「日本を目指したんですよ、VLSIを日本に学び、日本を抜くってね」
そんなサムスンに1970年代から1980年代にかけてNECとシャープが協力したことは歴史上の事実である。世界の半導体メーカー上位10社中6社が日本企業だった時代もあったが、いまやサムスンは半導体メーカーとして世界一、コロナ禍にあっても2022年1~3月期の連結営業利益は世界的な半導体需要で前年同期比50%増となった。
また1990年代に入ると韓国だけでなく中国にも工業技術や生産システムを教えた。三洋電機はいち早く安寧省の合肥市と合弁事業を展開、その三洋は東芝とともに、当時は得意な製品が電機扇風機、というレベルでしかなかった中国の美的集団(ミデア)にも協力した。
「個人的には不安でした。日本企業は1970年代から韓国に協力していましたが、1980年代には韓国もそれなりのものを作れるようになってました。たとえばゴールドスターの再生専用機とかテレビデオとか、なるほど値段なりとはいえよく作ってると思いましたよ」
ゴールドスターといっても若い人は知らないだろうが、現在のLG(LGエレクトロニクス)である。いまや世界に100以上の拠点を持つ多国籍企業だが、当時は「ラッキーゴールドスター(金星社)」という社名だった。LGはそのラッキーのLとゴールドスターのGである。いまはなき第一家電(2002年経営破綻)や新栄電機産業(2003年破産)といった家電量販店のはしりともいえるチェーン店でよく見かけたものだ。