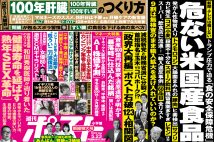生物学者・福岡伸一氏(共同通信社)
山を登り切った後に、別の山が見えた。新たな視点を得た福岡さんは体のあらゆる部分の細胞が絶え間なく合成と分解を繰り返して入れ替わり、そのことによって肉体のバランスが保たれているという「動的平衡(へいこう)」理論を提唱し、それこそが生命の特性であると突き詰めた。
坂本さんもまた、あらゆる音楽を生み出すうちに、音本来の豊かさは自然音にあるという気づきを得ていた。
「確かに楽器や電子機器が作り出す音はシンクロして美しくメロディアスに聞こえますが、どこまで行っても人工的なものに留まります。
坂本さんは枯れ葉を踏む、風が吹く、雨が降る、雪が降るといった自然音を収録して、新しい音楽の形を模索されていました。
デジタルを究めたわれわれがアナログへと回帰するという同じ経験を持っていたこともあってか、どんなテーマであっても対話の最後には人間の考えや言葉、論理を表す“ロゴス”と、自然そのものを示す“ピュシス”との対比に発展していきました。それもまた面白かった」
「ピュシス」であるがんとの対峙
《生きるというのは、一つの長い呼吸のようなものだと思うんです。(中略)『息をひきとる』とき、その生命は死を迎えるわけです。この動的平衡には抗えないし、また逆らわないほうがいいと思っています》
生前、福岡さんとの対話でそう語っていた坂本さんだったが、死を意識せざるを得ないような大きな変化が体に起きたのは中咽頭がんを患った2014年のこと。
「若い頃はそれなりに奔放な生活をしていたのが、息子さんの誕生を機にマクロビ食を実践するなど健康に気をつけるようになっていたこともあって、がんになったことに大きなショックを受けていらっしゃいました。
原因はなんだったんだろうか、HPVというウイルスの可能性があるのだろうかと心配されていたので、必ずしもそれが原因になっているわけではないということ、長く生きれば生きるほどがんは発生しやすいという生命の必然を話したことを覚えています」