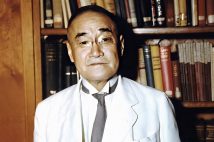三田紀房氏のXより
この連載は、佐渡島さんに面白いと言わせることが第一関門になります。
さて、どうするか。佐渡島さんは、東大に合格すること自体には何の関心もない。そこでこんなプロットを考えてみました。
舞台は、経営がうまくいかず潰れそうなっている偏差値底辺高。そこを再建させるための手段として、底辺の生徒を東大に合格させるというのはどうか。つまり、物語の主軸は「学校再建」で「東大合格」は手段に過ぎないということです。
その話をすると、初めて佐渡島さんも食いついてきました。
「それなら面白くなりそうですね」
そこからは一気に転がり始めました。
当時、経営がうまくいかない学校法人が、学校自体を解散して持っていた資産を売却したという話をニュースで知り、その事案に関わった弁護士から学校の再建方法についてレクチャーを受けることができました。そこで学校を再建する過程 についても知識が得られたことで、本格的に執筆に取り組む準備が整いました。
「バスの行き先理論」でアンケート急上昇!
──こうして2003年、『ドラゴン桜』の連載がスタートする。主人公は桜木建二、元暴走族の弁護士である。経営不振のため倒産の危機にさらされている龍山高校に、破産管財人としてやってきた。単なる債権整理より学校の建て直しに成功すれば、弁護士としての知名度が上がると考えた桜木は、落ちこぼれ生徒を「1年で東大に合格させる」と宣言し、その宣言どおり合格させる。
いよいよ連載が始まったものの、『ドラゴン桜』は当初、読者の反応は今ひとつでした。作品のテーマが「学校を再建する話なのか、東大合格を目指す話なのか、よくわからない」という書き込みがあるアンケートはがきがたくさん届いていたのです。
言われてみれば、その通りだったんです。元々、僕の中では「教師もの」として生まれた企画だったのが、編集の佐渡島さんに面白いと思わせるために、学校再建という当初は考えていなかった要素が加わった。そのため、どっちつかずのスタートになったことは否めません。
今から思えば、この時点では本気で読者に向き合っていなかったんです。読者のことを考えれば、まずはテーマをもっと明確にさせなければいけない。それに気づいて、ストーリーを大きく修正しました。
具体的には、水野という女子生徒が、桜木に対して「東大のどの学部を受けるの?」と尋ねる場面を作りました。これがポイントです。水野は勉強が苦手、とりわけ理数系はまったくダメな生徒です。当然、彼女は自分が受験するのも、文科系 だと思っているのですが、桜木がこう言い放ちます。
「お前らが受けるのは理科一類だ」