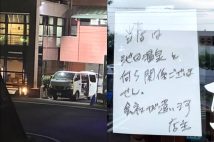覇権国家の道を歩んだアメリカが姿を変えるなか、改めて日米関係の行方が問われている(時事通信フォト)
昭和100年に当たる2025年、日本は戦後80年を迎える。諸外国では戦争が相次いで起き、帝国主義の論理が甦っている。覇権国家の道を歩んだアメリカが姿を変えるなか、改めて日米関係の行方が問われている。そうしたなか、元外務省主任分析官で作家の佐藤優氏と思想史研究者の片山杜秀氏が「昭和100年」を振り返り、討議した。対談内容をまとめた書籍『生き延びるための昭和100年史』より、一部抜粋、再構成して紹介する。【全3回の第2回。第1回を読む】
保護主義大統領三代
片山杜秀(以下、片山):ドワイト・アイゼンハワーは昭和28年、国連総会で「平和のための原子力」演説をしますが、その後、原子力の平和利用の理念は米ソ冷戦で遠くなっていきます。
佐藤優(以下、佐藤):はい。ジョン・F・ケネディ政権下の昭和37年、キューバ危機で核戦争の一歩手前まで緊張が高まりました。ドブルイニンなどソ連の高官がうまく立ち回らなければ、核戦争が起きて3~4億人の命が失われた可能性があったと思います。
そしてベトナム戦争の本格介入、泥沼化への流れは、軍事費の増大によるアメリカ経済の陰り、覇権国家の地位の揺らぎにつながります。
片山:リチャード・ニクソン大統領が1ドル360円の固定相場から変動相場に移行しました。ニクソン・ショックは世界経済を大きく変えます。
佐藤:ベトナム戦争で疲弊する自国経済を守る方向に舵を切ったわけです。同時にニクソンは10%の輸入課徴金を設定します。トランプ関税に通じる保護主義の前例です。