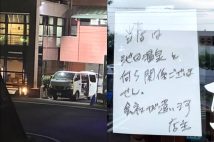そう言えば、この項を書いている現在、日本列島は猛暑に襲われ農業関係者は高温がコメの不作につながるのではないかという危惧を抱いている。みんながあたり前だと思っているこの「常識」が、ほんの数十年前はそうで無かったということは自覚されているだろうか? たぶん、ほとんどの人が自覚していないだろう。コメ(イネ)はそもそも熱帯原産の植物である。ということは、温帯の日本がいくら暑くなったところで深刻な影響を受けないはずではないか。それなのになぜ影響を受けるのか?
じつは、いま日本でもっとも人気のあるコシヒカリなどは、そもそも冷害の影響を受けにくいように品種改良されたものなのである。つまり、原種のコメと違って「寒さには強いが暑さには弱い」。だから異常高温だと不作が心配になるわけだ。しかし、こうしたコメができたおかげで日本の稲作から冷害による不作はほぼ追放されたのである。
江戸時代、現在の岩手県にあった南部藩では、ほんの少し寒冷になるだけでコメが不作となり多くの人間が餓死した。昭和になっても、冷害による不作は東北の民をおおいに苦しめた。二・二六事件が起こったのも、原因の一つに東北の冷害があったと言われている。事件を起こした青年将校には、東北農民の困窮をなんとか救わねばならないという使命感があったからだ。
それが「昔の話」になったのは、以前紹介したように戦前に農林水産省の技官であった並河成資が冷害に強いイネを開発したおかげである。にもかかわらず人間はそれがあたり前、つまり常識になると、ほんの数十年前まったく違う常識があったことを忘れてしまう。その「常識の変遷」こそ歴史そのものなのだが、それがまったくと言っていいほど理解されていない。
GHQと左翼学者の陰謀
人種差別の話はどこへいってしまったのだと思っている人がいるのかもしれないが、じつは話は変わっていない。現代ではアメリカでもイギリスでも有色人種の大統領や首相があたり前になった。それが「いまの常識」だ。しかし、ほんの百年前までは有色人種を人間以下の動物だと考えていた人々が世界を支配していたのだ。しかも彼らは、それを正当な行為だと信じていて、たまたま有色人種のリーダーの立場に立った日本人がいくら口を酸っぱくして説得しようとしても、その態度を変えようとしなかった。それが当時の「常識」なのである。その「昔の常識」を認識しない限り、歴史など分析できるわけが無いではないか。
しかし、これを読んでいるあなたがおそらくいま痛感されているように、これまで日本の歴史学界はそのことに触れてこなかった。このクリストファー・ソーンの『太平洋戦争とは何だったのか』について、書評を担当した国際政治学者の猪口邦子上智大学名誉教授は次のように述べている。
〈戦争には正義に満ちた論理があるはずだが、それは白人同士の場合のことであり、極東戦争はアジア人種蔑視の力学に浸潤された人種差別戦争の面が強かった、というヨーロッパの歴史家による議論は、やはり勇気ある主張であると言わなければならない。
それは、あまりにも明らかでありながら、広くタブーとなっていた史観である。〉
(『週刊朝日』1989年3月31日号書評欄より抜粋)
後半にご注目いただきたい。閉ざされた歴史学界では無く外から客観的に見れば、誰がどう見ても「人種差別戦争の面が強かった」ということが「あまりにも明らか」だったということだ。しかし、それがなぜ日本人の常識とならず「タブー」となってしまったのか?