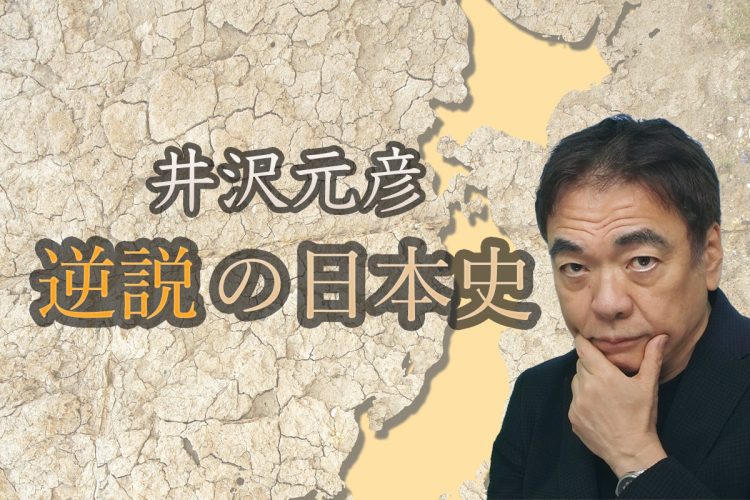作家の井沢元彦氏による『逆説の日本史』
ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十五話「大日本帝国の確立X」、「ベルサイユ体制と国際連盟 その11」をお届けする(第1462回)。
* * *
前回に引き続き、イギリスの歴史学者クリストファー・ソーン(1934~1992)の『太平洋戦争とは何だったのか』(市川洋一訳 草思社刊)から、人類の人種差別撤廃問題に関する部分を紹介しよう。
〈オーストラリア首相ロバート・メンジーズは一九四〇年(大東亜戦争開戦の前年。引用者註)に、日本人の「顕著な劣等感」から考えて、「中国問題解決に何か援助の手をさしのべて友好的な態度を見せたり……また日本の貿易上の野心を適当に認めてやりさえすれば、極東の平和は簡単に達成できるだろう……」と書いている。日本の攻撃開始二、三週間前ですら、アメリカ国務省の極東特別部顧問スタンレー・ホーンべックは、東京の目的は根本的にアメリカの利害とは相容れないと確信していたにもかかわらず、日本の好戦的な態度をたんなるこけ威しにすぎないとして無視していた。チャーチルもまた、真珠湾攻撃のほんの四日前に国防委員会で、日本の攻撃は「とても起こりそうにもない偶発事件」だと述べていた。〉
では、なぜそんな強い確信が英・米・豪の「アングロサクソン同盟」にあったのか?
〈このような確信は、戦争になれば日本はたちどころに敗れるだろうという、しばしば口にされた意見とならんで、一つには日本人を人種的に劣等視する態度から出ていることが多かった。(中略)チャーチルにしても、日本側がどのような動きに出ようと、英国海軍の最新鋭艦からなる小艦隊だけで十分「決定的な抑止力」になるだろうと信じていた。この確信から、彼は『プリンス・オブ・ウェールズ』と『レパルス』を派遣し、結果、ほとんど壊滅的打撃を受けることになったのである。オランダのウィルヘルミナ女王も、ドイツが敗れたら日本を片づける時期が来るだろう、そのとき西側は「鼠のように彼らを溺れさせ」ればよいのだと信じていた。〉
(引用前掲書)
つまり、彼らの「確信」は「日本人は(それ以外の有色人種も)人間以下で、サルやネズミのような動物である」という人種差別的感覚に基づくものなのである。これも正確に言えば前回述べたように、彼らはこういう考え方を人種差別とは夢にも思っていない。
ここは重大なことなので前回に続いて繰り返すが、人種差別というのは「人間の種類に基づく差別」であって、有色人種は「人種」では無いから「人間とサルを区別すること」と同じで、彼らはまったく平気だし良心の呵責も感じないのだ。アメリカ人の「ご主人様」が女性の黒人奴隷になにをしたか、あるいはオーストラリアの白人が先住民アボリジニをどう扱ったか、もう一度思い出していただきたい。
また、『逆説の日本史 第二十五巻 明治風雲編』で詳しく触れた「黄禍論」も思い出していただきたい。十九世紀末からヨーロッパで唱えられた人種警戒論で、最初は中国がヨーロッパの脅威となるという発想だった。言うまでも無く、ヨーロッパには十三世紀にモンゴルに攻められて大敗した歴史がある。しかし、その中国が日清戦争で日本に敗れて没落した結果、「黄禍」とは日本のことになった。
とくに日露戦争開戦寸前、ロシア帝国の君主だったニコライ2世は日本人を「黄色いサル」と呼んでいた。そもそも黄禍論はドイツが発祥の地であり、アングロサクソン系だけで無くゲルマン系もスラブ系も、ラテン系を除く白人はそうした強い「人種差別感」を持っていた。それがこの時代の戦争勃発も含めたすべての問題の根源にあるという歴史的認識が必要なのだ。
この『逆説の日本史』シリーズでたびたび強調してきたことだが、歴史の分析には「当時の人の気持ちになって考える」ということが絶対に必要である。そうしなければ、歴史の真相とはまったく違った結論に陥ってしまう。たとえば、「徳川五代将軍綱吉は、生類憐みの令を発したから愚か者だ」というような決めつけだ。最近は私がいろいろな場所で「それは違う」いや「むしろ逆だ」と言っているので「綱吉はむしろ名君」だという認識が広がりつつあるが、昔はそう言っただけでバカ者扱いされた。
そもそも武士は「人殺しが仕事」であった。それが「常識」だったから、現在のような人命尊重の世界に変えるには、とりあえず「犬を殺しても死刑」という「劇薬」のような法律が必要だったということだ。古くからの読者にはこれ以上説明する必要は無いと思うが、こういう考え方に納得できない人は、ぜひ初心者向けに書いた『コミック版 逆説の日本史 江戸大改革編』(小学館刊)をご覧いただきたい。