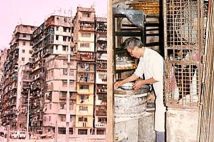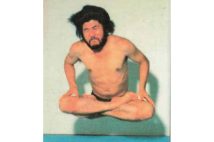女子高生は41日間にわたり監禁された(写真はイメージマートより)
実行犯の言動を裏付ける、これだけの“証左”
女子高校生を監禁し、ときどきクルマに乗せて町内を連れまわしたりしたということは、実行犯である数人の少年たちだけの秘密ではなく、彼らのすそ野にいた街の少年たちもその事実を知っていたことがわかっている。まるで、ギャング映画のワンシーンのようなことを実際にしでかし、虚勢をはるための道具に女性を利用したのである。
加害少年にとってのハクづけは、人より少しでも悪いことをすることだった。そうすれば、 一目置かれる存在になった。それが彼らの自己実現でもあり、勝ち取るべき価値だった。
「わかるような気がする。グループを形成したときには、普通だったら、こんなのおもしろくもねえって誰かが言えば、グループにならない。今回の場合は、誰かが自分より特技があるとか、違うところを持ってるとか、そういうところで敬われるわけではないんだから。
だから、やはり主犯格の彼はそういうふうにせざるをえなくなってきたんじゃないか。だんだん、教祖を演じるというか、そのためには普通のことをやってたんじゃ、教祖になれないからね。それは、少年の世界だって、大人の世界だって同じですよ」
そこにも、シンナーなどのクスリが関係している。
「彼は自分は万能感を持った人間であるということを信じ込んでいる。だから、まわりの人間はみんなバカだと思っている。これは薬物依存の共通した発想なんですよ。自分を正当化しなくてはならない。次第とそういうふうになってしまう。自分はなにも悪くないんだという。否認の変形と言ってもいい。
つまり、そうしてクスリを使える理由づけをどんどんつくっていくわけです。自分は正しくて、相手はバカだという、正しくないんだという。そういう論理が成り立たないといけなくなる。これは犯罪だとか、悪いことをやっているんだとか、そういう意識を最初は持っていたかもしれない。
でも、だんだんそれが大きくなってくると、正当化のために余計なことを背負うことになる。バカをつくんなきゃいけない。自分が神だと思っちゃう妄想を抱いたときにはそうなる」
(第4回に続く)
【著者プロフィール】
藤井誠二(ふじい・せいじ)
1965年愛知県生まれ。高校時代より社会運動にかかわりながら、取材者の道へ。著書に、 『殺された側の論理』(講談社プラスアルファ文庫)、『光市母子殺害事件』(本村洋氏、宮崎哲弥氏と共著・文庫ぎんが堂)、人物ルポ集として、『「壁」を越えていく力』(講談社)、『路上の熱量』(風媒社)、『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館新書)、『体罰はなぜなくならないのか』(幻冬舎新書)、『死刑のある国ニッポン』(森達也氏との対話・河出文庫)、『沖縄アンダーグラウンド―売春街を生きた者たち』(集英社文庫)など著書・対談等50 冊以上。愛知淑徳大学非常勤講師として「ノンフィクション論」等を語る。ラジオのパーソナリティやテレビのコメンテーターもつとめてきた。
「薬物依存症」から社会復帰を目指すリハビリ施設・ダルクホーム(NPO法人「東京ダルク」HPより)
女子高生コンクリート詰め殺人事件・判決公判で傍聴券の抽選をする人たち/東京・霞が関の東京地裁(時事通信フォト)
女子高生コンクリート詰め殺人で、初公判が開かれた東京地裁法廷=1989年7月31日午後(共同通信)
行方不明だった女子高生がコンクリート詰め遺体で発見された現場=1989年3月30日(共同通信)
女子高生がコンクリート詰め遺体で発見された東京都江東区若洲の埋立地=1989年3月30日(共同通信)
女子高生は凌辱の限りを尽くされたという(写真はイメージマートより)