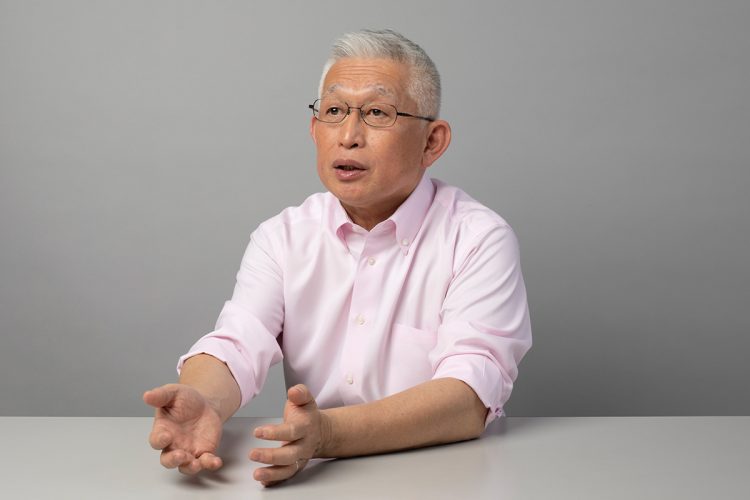市の職員たちを巻き込みながら、子ども政策や福祉政策など数々の市政改革を実現させた泉氏
──各省庁の官僚はそれぞれの分野のエキスパートですから手強い。
国政は複雑で多種多様で、しかも行政は激しい縦割りです。地方自治体の首長は大統領制的なシステムの中で一元的に権限を行使できるけれど、国会議員は立法府なる合議体組織の一員に過ぎません。
新著『公務員のすすめ』でも書きましたが、地方自治体の首長には、方針決定権・人事権・予算編成権がありますから、これらの権限を行使して市政を改革していくことができます。
実際、私も大胆に政策を転換させて予算を組み替え、子ども政策の予算を125億円から297億円まで2.4倍に増やし、子ども政策を担当する職員の数も39名から150名とおよそ4倍に増やしました。優先させるべき政策に財源と人材を集中させて、明石市の人口増と経済の好循環へと繋げた。やる気さえあれば、その権限を適切に行使して大胆に方針を転換できるのが首長です。
一方、総理大臣の場合、首長に近いような形での権限行使が本来であれば可能です。ところが、日本においてその権限を行使した総理は、ほとんどいないと言っても過言ではないでしょう。近年ではもっとも権限を行使したはずの安倍晋三元首相でさえ、消費税の増税方針においては最終的に財務省に従わざるを得なかったと思うと、行政に対して全責任を負った日本のトップは、戦後の歴史上、存在していないのではないでしょうか。結局は、XYZの連立多元方程式の解を解こうとすらせず、「ここに答えがありますよ」と官僚に言われると「そうか」と従ってしまう。
「いや、ちょっと待って。自分たちで解を導き出して、方向づけをしていくから」というような政治の動きが、衆議院議員だった20年前と比べてさらに弱くなり、官僚主導がますます強まっているように感じます。