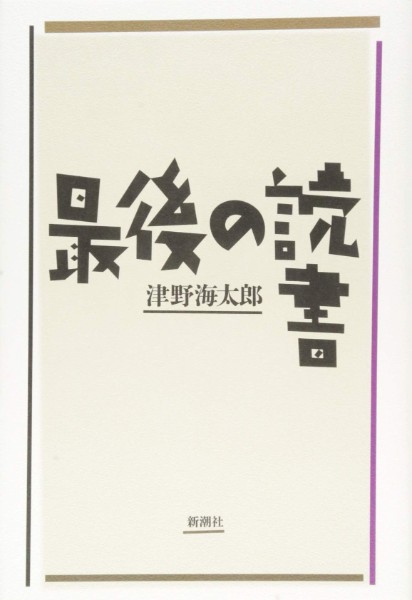『最後の読書』津野海太郎・著
【書評】『最後の読書』/津野海太郎・著/新潮社/1900円+税
【評者】関川夏央(作家)
蔵書家というものがいた。本に飢えた戦中を過ごし、戦後はむさぼるように読んだ。高度成長期には大量生産された本を買っては売り、売っては買ううちに本は際限なく増えた。背景には「昭和戦後」の「教養主義」がある。一九三〇年代生まれの本好きがこのコースを歩みがちだった、と三八年生まれの著者・津野海太郎はいう。三四年生まれの井上ひさしの蔵書は十四万冊に達した。
本は場所を取る。一部屋つぶすくらいでは済まない。家族が迷惑がる蔵書処分は「終活」の柱だ。しかるに古書業界は事実上消滅し、図書館は本の寄付を断る。捨てるほかないとは情けない。
津野海太郎も無類の本好き、歩きながら読書する少年だった。長じて編集者となり書き手となっても歩行読書癖はつづいた。独身時代には頻繁な引越しのせいか蔵書は三、四千冊にとどまったが、五十歳を過ぎて結婚すると七千冊まで増えた。
二千冊処分してそれ以上はあきらめたが、読書はとまらない。「先もないのに、そんなに本ばかり読んでどうするの」という内心の声を、今年八十一歳の著者のみならず、年配の読者はひとしく聞く。「いつか何かの役に立てる」という野心・欲望はとうに消えたのに、読むのをやめられない。時代精神の刻印とは、かくも濃い?
津野海太郎の場合、さらに「病」は深刻だ。自分の少年時代、アメリカ以外みんな貧乏だったという記憶が、デ・シーカの映画『ミラノの奇蹟』再見で喚起されると、ミラノで「カトリック左派」の拠点である書店の運動に身を投じた須賀敦子の作品再渉猟に走る。さらに戦後日本の「コミューン」に興味はおよんで、獅子文六、網野善彦、『蟻の街のマリア』北原怜子へと話はめぐって須賀敦子に回帰する。
そんな、根拠ある飛躍そのものが文学だと私は思う。「文学産業」は滅び、蔵書は打ち捨てられても、文学は「細々と」不滅でありつづける。
※週刊ポスト2019年2月1日号