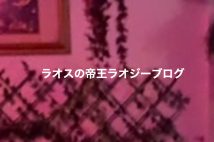日本は油断していた。このビリー・ヒューズの政治力を認識していなかった。オーストラリアは当時「英連邦」の一員であり、当然日本政府代表団は、オーストラリアは本国イギリスの判断に従うと考えていた。実際、最終決議の場ではイギリスが代表して投票する形でヒューズは参加メンバーですらなかった。ところが、まずイギリス代表がヒューズの強引な根回しに屈服してしまった。
この問題に関する最初の全体協議が行なわれる直前の二月八日の午前、パリでアメリカ代表団の一員でウィルソン大統領側近のエドワード・M・ハウス“大佐”と、デイビッド・ミラー法律顧問らが日本の人種差別撤廃提案について協議していた。
じつは前回そのまま「大佐」と紹介してしまったが、彼は軍人では無く外交官である。ケンタッキーフライドチキンの創始者をカーネル・サンダースと呼ぶように、カーネル(陸軍大佐)というのは親しみを込めたニックネームである。ちょうど日本で、陸軍大将でも無い酒場のマスターを「大将」と呼ぶようなものだ。とにかくアメリカ代表団が協議していたところへ、イギリス全権の一人であるロバート・セシル子爵があたふたと入ってきた。
〈セシルは、イギリスがこの提案に賛同することはない、いかなる形でも、と述べた。それというのも、白豪主義をとるオーストラリアを代表するビリー・ヒューズ首相が頑強に反対している以上、イギリスとしては日本の提案に賛成するわけにはいかないというのである。〉
(『人種差別撤廃提案とパリ講和会議』廣部泉著 筑摩書房刊)
具体的にヒューズ首相がどう動いたかは、引用した『人種差別撤廃提案とパリ講和会議』に詳しく語られているので、興味ある方はそちらをご覧いただきたい。ポイントは、イギリスが絶対反対ならアメリカが賛成するわけにはいかない。そうなればウィルソン大統領の最大の目的である国際連盟設立が夢となってしまう、ということだ。
ここに至ってアメリカ代表は、なにがなんでも日本の提案を封じ込めなければいけない立場に追い込まれた。逆に言えば、そのアメリカ側の弱点を巧みに突いたヒューズ首相の政治力の「勝利」でもあった。もっとも、この人種差別大国の「勝利」によって、人類の悲願であったはずの人種差別撤廃は何十年も遅れることになった。
ところで、オーストラリア人の「アボリジニ狩り」。あなたはどういう感想を抱くだろうか? 日本語でこの蛮行を呼ぶとしたら、なんと言うか? 「鬼畜の所業」というのが、日本語としてもっともふさわしい表現ではないだろうか。
だからこの後しばらくして、日本は彼らと戦争におよぶにあたって彼らのことを「鬼畜米英」と呼んだのである。
(第1458回に続く)
【プロフィール】
井沢元彦(いざわ・もとひこ)/作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。
※週刊ポスト2025年6月27日・7月4日号