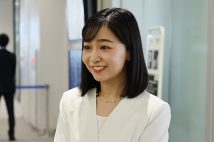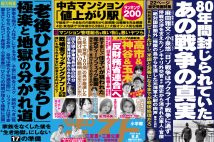ここで団塊の世代も若い人も、生まれてからNHK連続テレビ小説や映画などで何度も見たはずの、昭和十六年十二月八日の「開戦シーン」を思い浮かべていただきたい。ラジオから興奮したアナウンサーが「大本営海軍部発表、本八日未明、帝国海軍は米国真珠湾において敵艦隊の撃滅に成功せり」などと叫び、「この日、太平洋戦争が始まりました」などというナレーションが流れるのが定番だったはずだ。
しかし、実際には始まったのは「大東亜戦争」で、その証拠に戦場は太平洋だけで無く、マレーシア、シンガポール方面つまりアジアも含まれていた。こんなナレーションを書く脚本家は、じつは戦後八十年以上経っても「アメリカの陰謀」にいまだに乗せられているわけだ。
では、なぜアメリカは「大東亜戦争」という言葉を消そうと考えたのか。
日本史で同じようなケースがあるので紹介しよう。幕末の話である。最後の将軍・徳川慶喜は、倒幕を狙う長州をこの世から消し去ろうと、長州征伐を実行した。
じつは「征伐」という言葉には、特別な意味がある。「天皇が許可した討伐」ということだ。戦国時代でも、関白・豊臣秀吉が関東の北条氏を滅ぼすに際して「小田原征伐」と言ったのもそういう意味がある。つまり慶喜が「長州征伐」と言えたのは、幕府支持で長州嫌いの孝明天皇がそれを認めたからである。この時点で長州藩は「朝敵(天皇家の敵)=絶対悪」だった。
では、なぜそういうことになったかと言えば、長州藩が挙兵し天皇を長州に連れ去ろうとしたからで、このとき長州軍は京都御所を攻めて薩摩藩と会津藩の連合軍に撃退される。これをいまでも歴史学界では「禁門の変(蛤御門の変。1864年)」と呼んでいる。もうおわかりだろう。八十年どころでは無い、百五十年以上も歴史学界は「長州の陰謀」に乗せられているわけだ。
「変」という言葉は、古くは「禁闕の変(1443年)」あるいは「本能寺の変(1582年)」のような「事件」に使われる言葉で、このとき長州は正規兵を使って京都御所を襲撃したのだから、日本語としては「長州の乱(叛乱)」と呼ぶのが正しい。しかし、そう呼ぶと長州がこのときじつは朝敵であったことがバレてしまうので、彼らは明治維新後に天下を取ったときに、この言葉を使わせまいとしたのである。
また「長州征伐」についても長州人は「言い換え」させようとした。「四境戦争」という用語を使って、である。
〈四境戦争 しきょうせんそう
第二次長州征伐(1866)の長州藩での呼称。大島口、芸州口、石州口、小倉(こくら)口の四境で、幕府軍と長州軍の戦闘が行われたため、こうよばれる。〉
(『日本大百科全書〈ニッポニカ〉』小学館刊 傍点引用者)
「長州は東西南北から一挙に攻められたが、一致団結して敵を撃退した」ということだ。たしかに戦い自体はそうしたものだったが、この言葉を使うとそれは「天皇が許可した公式な征伐だった」というニュアンスを消すことができる。だから長州人はなんとかこれを定着させようとしたのだが、さすがにこの試みは失敗した。しかし「禁門の変」については成功し、現代の歴史学界も二十一世紀になったというのに長州藩の陰謀に乗せられたまま、ということだ。