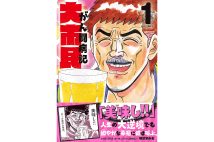名古屋場所14日目の西の溜席の最前列、「着物美人」として知られる女性がピンクの鮮やかな洋服姿で登場
65歳定年を控える多数の親方
そうした再雇用の弊害もある。相撲協会に親方として残るためには、105ある年寄名跡のいずれかを取得する必要があるからだ。数に限りがあるため、参与として残る親方が増えれば、協会に残りたい力士が年寄名跡を取得できないという構図になるのだ。
この2年ほどで65歳の定年を迎える親方は、大嶽(元十両・大竜)、白玉(元前頭・琴椿)、常盤山(元小結・隆三杉)、陣幕(元前頭・富士乃真)、勝ノ浦(元前頭・起利錦)、春日野(元関脇・栃乃和歌)、境川(元小結・両国)、粂川(元小結・琴稲妻)、芝田山(元横綱・大乃国)、錦戸(元関脇・水戸泉)と10人もいる。
「今年9月に65歳の定年を迎える大嶽親方は、片男波部屋付きの熊ケ谷親方(元前頭・玉飛鳥)と年寄名跡交換。大嶽部屋を継承させ、大嶽親方は熊ケ谷として再雇用されて部屋付き親方として残ることが名古屋場所後に発表された。
このように、全員が参与として協会に残れば、現役力士が協会に残ろうとしても年寄名跡の取得が難しくなる。結果、現役を引退できず、大関を陥落した力士が十両で取り続けるようなケースも出てくる。
ただでさえ近年は豊山や阿武咲、豊ノ島、松鳳山、千代大龍、常幸龍などが年寄名跡を手に入れることができずに廃業していった。これまでは再雇用を選ばずに後進に道を譲る親方もいたが、70歳定年になれば年寄名跡不足はさらに拍車がかかる懸念がある」