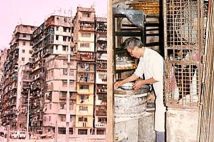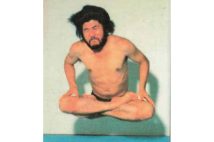女子高生がコンクリート詰め遺体で発見された東京都江東区若洲の埋立地=1989年3月30日(共同通信)
薬物問題と非行問題の関係性
しかし、薬物と少年たちの「非行」をたやすく結びつけるのはよくない、と近藤氏は言う。
「薬物問題と非行問題は混同してはいけない。非行というのは、薬物依存の結果起こる症状だとして、症状をとらえて非行、非行と言っている。あるいは非行に走ったからシンナーを吸ったんだとかいう考え方。シンナー吸って、家を壊したりしている少年をとらえて、シンナーイコール非行少年ということになってしまっているけれど、そこは分けて、まずはどうしてシンナーを吸うようになったのかを考えて、問題をピックアップしなければならない」
近藤氏は、まず家庭の中で少年を取り巻く「不安」を理由に挙げた。
「家族の“ルール”というのはある意味では大事。昨日はほめられた。今日は酔っぱらった親父に殴られた。これを繰り返されると、子どもが予測つかないのね。つまり、子どもというのは成長の過程で、こういうことした結果、こういうふうに怒られるというふうに予測するようになる。それが予測できて先のイメージというか、自分のとった行動の意味、先の予測を立てる。
しかし、それができないと不安になる。いちばん悪いのは不安を持って生きること。だから、不安をなくすために薬物依存にいく。それは要因じゃないけれど、入り込む種になってしまっている」
この論理も、女子高校生を監禁した部屋の主であったCの家庭と符合する。彼の父親は毎日のように泥酔して帰宅、ときには母親から息子の失態を聞き、体罰を加えることもあった。しかし、あるときを境にそのやり方を放棄。理由をたずねる息子に「そうある本に書いてあったから」としか答えなかった。裁判の中でそのCはこの件で父親に対して信頼が持てなくなったことを陳述している。
「この時期というのは、親よりも友だちをかばう時期。そして、グループになりたがる。そこで大事なのは、その中で自分がいいかっこできるかってこと。オートバイにいくやつはオートバイにいくだろうし、ヤクザの好きなやつはヤクザにいくだろう。それは子ども一人ひとりが持っている才能の問題だから、そこにいくのがいいとか悪いとかそういう問題ではなく、その中での自分のプライドの問題だと思う。いいプライドを持てない子っていうのは、必ず環境のどこかに問題がある」
人生をやりなおすためにベストな方法とは
では、シンナーなどによるドラッグ・アディクションの共通病理に対抗するためにはどうしたらいいのだろうか。
「そういう少年が良く変わっていくためには、前に言った4つ(編集部註:自由、成長、創造性、善意)を取り戻すことが大切。でも、それは少年院や刑務所ではだめ。自由のないところでは、自由を選択できないんだから。自由とか創造性とかないところでは反省にならない。反省させられるハメになったとしか思わない。ベストな方法とは、彼らがクスリを使ったときの年齢に戻らなくてはいけない。それが彼らの人生のスタート。その年齢からやり直すことです」
薬物依存が引き起こす人間破壊の論理で、この事件のすべてが説明できるわけではない。だが、僕たちが見落としていた数々の視点がそこにはあった。
(了。第1回から読む)
【著者プロフィール】
藤井誠二(ふじい・せいじ)
1965年愛知県生まれ。高校時代より社会運動にかかわりながら、取材者の道へ。著書に、 『殺された側の論理』(講談社プラスアルファ文庫)、『光市母子殺害事件』(本村洋氏、宮崎哲弥氏と共著・文庫ぎんが堂)、人物ルポ集として、『「壁」を越えていく力』(講談社)、『路上の熱量』(風媒社)、『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館新書)、『体罰はなぜなくならないのか』(幻冬舎新書)、『死刑のある国ニッポン』(森達也氏との対話・河出文庫)、『沖縄アンダーグラウンド―売春街を生きた者たち』(集英社文庫)など著書・対談等50 冊以上。愛知淑徳大学非常勤講師として「ノンフィクション論」等を語る。ラジオのパーソナリティやテレビのコメンテーターもつとめてきた。
世間を震撼させた女子高生コンクリート詰め殺人事件・判決公判で傍聴券の抽選をする人たち/東京・霞が関の東京地裁(時事通信フォト)
女子高生コンクリート詰め殺人で、初公判が開かれた東京地裁法廷=1989年7月31日午後(共同通信)
行方不明だった女子高生がコンクリート詰め遺体で発見された現場=1989年3月30日(共同通信)
女子高生は41日間にわたって監禁され、凌辱の後コンクリート詰めにされた(写真はイメージ)
女子高生は41日間にわたり監禁された(写真はイメージマートより)