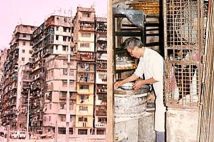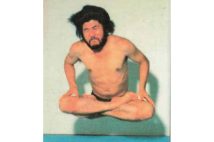ホテルのように綺麗な内装の介護施設(写真/イメージマート)
さらに牧野氏は、高級老人ホームの運営側が抱える構造的なリスクについても言及する。
「すべての高齢者施設に共通することだが、入居者は“有限”であり、いずれは健康を害し、亡くなる。デベロッパーは、本来的に医療や介護の専門家ではないため、提携医療機関に丸投げする形になる。極端な話として、入居者にはなるべく早く健康を害し、老人ホームから医療機関に移ってもらったほうが、部屋の回転率が上がり、その都度前払い金がたくさん入ってくるため、経営はうまくいく」
富裕層の高齢者の多くは、いざ健康を損ない、施設から出ることになっても、路頭に迷うようなことが少ないため、問題が表面化しにくい側面があるという。
「デベロッパーは“箱”から入るため、見た目が高級なものを作ることには長けているが、人間、特に老人の心理を深く理解しているわけではない。入居者側も、現役時代のステータス感覚で施設を選びがちだが、画一的な“高級”の押し付けでは、多様な個人の幸福にはつながらない。
特に、何百人もの入居者が同じ施設を共有するタワマン型では、コミュニティを上手く形成するのは難しいのではないか。施設側から“ほら、これが幸せでしょう”と提示される画一的な暮らしは、最初は良くても、その先には後悔しか残らない可能性もあるのでは」(牧野氏)
例えば、一般的なマンションでは隣人とのコミュニケーションは希薄になりがちだが、老人ホームでは共同生活が前提となる。しかし、タワマン型では『タテとヨコ』の関係性、つまり高層階と低層階での入居金の差が人間関係に影響を与えたり、隣室同士のトラブルが退去の原因になったりすることもあるのだろう。