野田聖子の最新ニュース/2ページ
【野田聖子】に関するニュースを集めたページです。

女性総理誕生に必要な自民党の「派閥」の変化 「お金とポストは男性が握る」現状の打破を
迷走を極める岸田政権。この状況を打破するのは、"ガラスの天井"をブチ壊す女性リーダーの登場ではないのか。自民党の野田聖子・衆議院議員、立憲民主党の辻元清美・参議院議員、共産…
2023.01.07 05:47

女性国会議員3人が語る「女性総理誕生」に必要な“議会と社会の改革” 子育てと政治の両立を
迷走を極める岸田政権。この状況を打破するのは、"ガラスの天井"をブチ壊す女性リーダーの登場ではないのか。自民党の野田聖子・衆議院議員、立憲民主党の辻元清美・参議院議員、共産…
2023.01.07 05:43

【野田聖子×辻元清美×田村智子】3議員が党派超えて語る女性政治家“ガラスの天井”
迷走を極める岸田政権。この状況を打破するのは、"ガラスの天井"をブチ壊す女性リーダーの登場ではないのか。自民党の野田聖子・衆議院議員、立憲民主党の辻元清美・参議院議員、共産…
2023.01.07 05:24

配偶者控除の次は何が見直しか 「男女共同参画白書」をきっかけに広がる不安
20代男性の約7割、女性の約約5割が「配偶者や恋人がいない」という調査結果が話題になった令和4年版『男女共同参画白書』(内閣府)だが、社会や人間関係の変遷を調査・分析するだけで…
2022.06.25 13:03

働く女性はおじさんと似てる? 野田聖子氏のジェンダー平等論と小池百合子氏との対立軸
日本初の女性総理候補と目される政治家たちの本音を聞く連続インタビュー。第3弾に登場するのは、過去に何度も断念した自民党総裁選に昨年やっと出馬を果たした野田聖子・男女共同参画…
2022.03.30 17:19

野田聖子氏が語る女性議員と結婚のリアル 離婚したら「お帰り!」の声も
日本初の女性総理候補と目される政治家たちの本音を聞く連続インタビュー。第3弾に登場するのは、過去に何度も断念した自民党総裁選に昨年やっと出馬を果たした野田聖子・男女共同参画…
2022.04.01 18:46

高市氏、小池氏、辻元氏と競わされ…「初の女性総理候補」野田聖子氏の30年
日本初の女性総理候補と目される政治家たちの本音を聞く連続インタビュー。第3弾に登場するのは、過去に何度も断念した自民党総裁選に昨年やっと出馬を果たした野田聖子・男女共同参画…
2022.03.28 21:56

“政権No.2”野田聖子氏が明かす 自民党の女性議員が妙にマッチョになる理由
日本初の女性総理候補と目される政治家たちの本音を聞く連続インタビュー。第3弾に登場するのは、過去に何度も断念した自民党総裁選に昨年やっと出馬を果たした野田聖子・男女共同参画…
2022.04.01 18:41
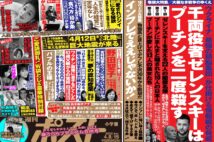
「週刊ポスト」本日発売! プーチンを暴走させた日本人ほか
3月28日発売の「週刊ポスト」は、世界の安全保障だけでなく、各国の経済や政治にも影響を与え始めたウクライナ戦争の行方と、われわれ市民の自衛策を徹底検証する春の合併特大号。"千両役者"ゼレンスキー大統領を…
2022.03.25 13:16

野田聖子独白70分 総理をめざす女たちの「悪名」と「宿命」
日本初の女性総理候補と目される政治家たちの本音を聞く連続インタビュー。第3弾に登場するのは、過去に何度も断念した自民党総裁選に昨年やっと出馬を果たした野田聖子・男女共同参画…
2022.04.01 18:40

稲田朋美独白60分 「ポスト岸田」高市早苗・野田聖子両氏との大きな違い
日本初の女性総理候補と目される政治家たちの本音を聞く連続インタビュー。第2弾は、かつて「安倍晋三・元首相の秘蔵っ子」「タカ派のアイドル」と呼ばれた稲田朋美・元防衛相(63)である…
2022.03.18 13:09

「ガラスの天井はなかった」高市早苗独白60分 野田聖子氏とは異なる女性論
世界では続々と女性リーダーが誕生しているのに、日本ではいまだ実現していない。それほどまでにこの国の「ガラスの天井」は硬いのか──。先の自民党総裁選で岸田総理に肉薄した高市早…
2022.03.08 13:37

野田聖子氏 石原派、石破派の残党集めで「野田派旗揚げ」なるか
総選挙が終わって自民党では"ポスト岸田"をにらんだ動きが始まっている。安倍晋三・元首相の後見によって総裁選で予想以上の健闘を見せた高市早苗・自民党政調会長が存在感を増してい…
2021.11.08 11:25

立憲民主党代表選、蓮舫氏への待望論なし 女性政治家の人材不足が課題
立憲民主党の枝野幸男代表が総選挙敗北の責任を取って辞任。後任代表候補には元総務政務官の小川淳也氏、党役員室長の大串博志氏が意欲を表明しているほか、馬淵澄夫・元国土交通相や…
2021.11.05 13:20

自民党総裁選、高市早苗氏は「弱者よりも国家」か 求められる「女性」への視点
29日に投開票を迎える自民党総裁選。河野太郎行政改革担当大臣、岸田文雄前政調会長、高市早苗前総務大臣、野田聖子幹事長代行4氏が熾烈な争いを繰り広げている。総裁選に女性候補2人…
2021.09.28 17:48

自民党総裁選の候補者討論 報ステとWBSの仕切りの差異は興味深かった
自民党総裁選をめぐる報道が連日繰り返されている。候補者でない人について思わず気になってしまうことも少なくないのではないか。作家で五感生活研究所代表の山下柚実氏が指摘した。…
2021.09.24 18:07

菅首相辞任で女性天皇議論も進展 誰が新総理になれば「愛子天皇」実現か
安倍政権以降、遅々として議論が進まず、事実上実現は不可能とみられてきた「女性天皇」。しかし、愛子さまのご成人前という"滑り込み"のタイミングで菅義偉首相が退任を表明。状況は…
2021.09.08 15:14

「岸田文雄氏の大局観は1点」ベテラン政治評論家が自民党総裁候補を採点
党役員人事や解散戦略など、政局をめぐる話題ばかりが先行した自民党総裁選は、菅義偉・首相の「不出馬表明」で新たな局面に突入した。9月17日の告示まで党内の綱引きは続きそうだが、…
2021.09.06 07:26

「ポスト菅首相」に急浮上 野田氏、稲田氏、小池氏、3人の女性候補
日本の政治は、言わずもがな"男社会"だ。しかし、いま急速に「初めての女性首相」を求める声が高まっている。菅政権の次は女性首相だろう──実は、自民党の男性議員の間からも、「女性…
2021.05.22 00:07

ポスト菅候補を採点 有力・河野太郎氏も対抗・野田聖子氏も評価は二分
政治家の「総理としての資質」を見抜くのは難しい。「平時」と「乱世」では求められる能力も違う。コロナ危機のさなかに就任した菅義偉・首相は官房長官時代に見せた「危機管理のプロ…
2021.04.29 15:51
トピックス
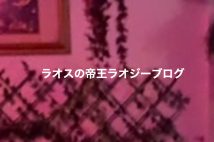
《昨夜の子は何歳だったんだ…との投稿も》「ラオスの帝王ラオジー」ブログの不正開設の疑いで61歳の男が逮捕 専門家が明かしたラオス児童買春のいま
NEWSポストセブン

【2・8総選挙「東京21〜30区」は波乱の展開】前回無所属で議席を守った旧安倍派大幹部は「東京最多の公明党票」に苦戦か 中道がややリードの選挙区も
NEWSポストセブン

《白シャツ女性に覆いかぶさるように…》エプスタイン・ファイルで新公開されたアンドリュー元王子とみられる人物の“近すぎる距離感の写真” 女性の体を触るカットも
NEWSポストセブン

《真美子さんが座る椅子の背もたれに腕を回し…》大谷翔平が信頼して妻を託す“日系通訳”の素性 “VIPルーム観戦にも同席”“距離が近い”
NEWSポストセブン

《“お前の足を切って渡すから足を出せ”50代姉を監禁・暴行》「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻 “恐怖の二世帯住宅”への近隣証言
NEWSポストセブン

【2・8総選挙「大阪11〜19区」の最新情勢】公明党の強力地盤「16区」で立憲出身中道候補の「維新逆転」はあるか 政治ジャーナリストが分析
NEWSポストセブン

〈今年も一年、生きのびることができました〉前橋スナック銃乱射・小日向将人死刑囚が見せていた最後の姿「顔が腫れぼったく、精神も肉体もボロボロ」《死刑確定後16年で獄中死》
NEWSポストセブン

国際ジャーナリスト・落合信彦氏が予見していた「アメリカが世界の警察官をやめる」「プーチン大統領暴走」の時代 世界の“悪夢”をここまで見通していた
NEWSポストセブン

《頬がこけているようにも見える》高市早苗首相、働きぶりに心配の声「“休むのは甘え”のような感覚が拭えないのでは」【「働いて働いて」のルーツは元警察官の母親】
NEWSポストセブン

井手上漠(23)が港区・六本木のラウンジ店に出勤して「役作り」の現在…事務所が明かしたプロ意識と切り開く新境地
NEWSポストセブン

長澤まさみ「カナダ同伴」を決断させた「大親友女優」の存在…『SHOGUN』監督夫との新婚生活は“最高の環境”
NEWSポストセブン

「口に靴下を詰め、カーテンで手を縛り付けて…」「意識不明の姿をハイ状態で撮影」中国人美女インフルエンサー(26)が薬物で急死、交際相手の男の“謎めいた行動”
NEWSポストセブン
