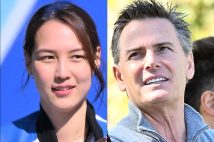コロナ禍、ウクライナ紛争、中国の爆買い、異常気象の「クワトロ・ショック」が食料に影響(写真/PIXTA)
自然の摂理に沿った農業が最も効率的
世界一保護が手薄な状況にもかかわらず、日本の農家や酪農家は、踏ん張っている。彼らは飼料や燃油価格の高騰にあえぎながらも、私たちの食卓に安全な肉や野菜を届けるべく、奮闘している。
その頑張りで、いまでも世界10位の農業生産額を達成している日本の農家はまさに「精鋭ぞろい」であると言って差し支えない。
特に近年、筆者が注目しているのは自然の摂理に従った農業を行う「アグロエコロジー」が日本各地で広がり、実践されていることだ。
その一例が、北海道で広がりつつある「放牧酪農」だ。これまで乳牛は牛舎で管理された状態で飼育されるのが一般的だったが、放牧酪農では牛を牧草地に放牧して自由な環境で育てる。
面積当たりの飼育頭数は従来の半分以下になるため、一見すると非効率に見えるが、メリットは大きい。その1つが飼料だ。牛のエサは輸入トウモロコシを配合した飼料を使うのが一般的だが、放牧で牧草を食べさせれば、その分飼料費を抑えることができる。牛舎の清掃など管理の手間も省けるため、人件費が減るのも利点だ。
実際に町を挙げて放牧酪農に取り組む十勝の足寄町は、町内で行われている農業の中で放牧酪農が最も大きな利益を上げているという。そうした成功例を聞きつけた新規参入希望者が順番待ちになるほど多数押し寄せた結果、町の人口まで増え始めた。
千葉県には、飼料に配合する輸入トウモロコシを米に変えた酪農家もいる。国産に切り替えることで、輸入飼料の価格が高騰してもびくともしない鉄板の経営を続けている。
こうした国内で奮闘する農家の取り組みを支援する自治体も増えている。千葉県いすみ市は、2012年に「環境保全型農業によるまちづくり」を宣言し、2017年から市内の学校給食すべての米を地元産の有機米に変えた。
安心安全な“本物”を作ってくれる国内の生産者を支えるためには、いすみ市のような自治体の存在に加えて、消費者が安全な農産物を買って食べ、支援することが何よりも肝要なのだ。