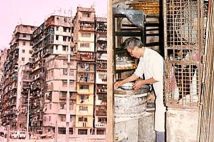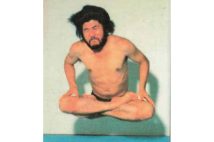おわかりだろう。菊地学説を唱えるような人間にとって、当時彼らが帰化人と呼ばれたことは自説の証拠となる歴史的事実、つまり史料なのである。歴史学者が史料を抹殺してどうするのか? 天に唾する行為ではないか。なぜそうしなければならないかを、菊地照夫項目執筆者は先の引用部分に続くところで次のように述べている。
〈「帰化」の語は、今日においても外国人の日本国籍取得を意味する法律用語として用いられるが、明治以降の「帰化人」の多くが朝鮮人・中国人であり、これらの人々を日本人と異なる、差別・蔑視(べっし)されるべき人々とする偏見が、日本の朝鮮・中国に対する植民地支配・侵略の思想的背景にあった。古代の渡来者を「帰化人」とみる歴史観は、このような東アジア近隣への日本の支配を歴史的に遡及(そきゅう)させて正当化していこうとする誤った観念に陥りやすいという指摘も考慮されるべきであろう。〉
回りくどい言い方だが、彼がなにを言いたいかはおわかりだろう。要するに「帰化人という言葉は朝鮮人・中国人に対する差別を助長する」から廃すべきだ、と言っているのだ。かつて、「めくら」という言葉は「身障者差別を助長する」から無くすべきだと主張した人間たちと同じ精神構造なのである。それが日本文化に対する大きな蛮行であり愚行であったことは、すでに述べたとおりだ。
もちろん、あらためて強調するまでも無いが、あらゆる差別はこの世から無くすべきである。もうお忘れになったかもしれないが(笑)、そもそも本章は一九一九年に日本が初めて世界に向かって提言した人種差別撤廃問題の話から始まっている。だから差別は無くすべきなのだが、日本人は言霊信仰の強い影響下にあり、往々にしてその手段を「言葉狩り」に求めてしまう。そのことが問題だと言っているのだ。
それにしても若い世代がすでにご存じないように、言葉狩りの猛威が日本を席巻したのは何十年も前であった。逆に現代では古い映画の放送にあたり「問題のある表現もありますが、当時の表現者の意図を尊重しそのまま放送します」などという形で、極力「言葉狩り」がなされないように社会のシステムが変わった。
そうした現状にくらべれば、いまだに言葉狩りが幅をきかせ「大東亜戦争」では無く「アジア・太平洋戦争」と言い換えるべきだ、などと主張する学者のいる歴史学界は、相当異様な世界だとわかるだろう。なぜそうなってしまったのか?
一つは、左翼歴史学者というのはマルクス主義の影響下にあり無神論的立場を取るから、どうしても宗教を軽視あるいは無視する立場を取るからだ。自分は宗教をまったく信じないというのは、個人の自由である。しかし、過去の日本人もそうであったと断定するのは大いなる間違いだ。むしろ日本人には日本人独特の信仰があり、「言霊信仰」にせよ「怨霊信仰」にせよ、その都度日本人を強く動かしてきた。そのことを無視しては日本史の探求などできるはずも無い。
もう一つは、歴史学界がきわめて風通しの悪い閉鎖社会であることだ。私は三十年以上前から「安土桃山時代」はおかしい、桃山という地名は秀吉の時代には無かったし、秀吉の権力の拠点は大坂にあったのだから「安土大坂時代」にすべきだと、口を酸っぱくして言っている。しかし彼らはこの中学生でもわかるおかしな点を、決して改めようとしない。
そうした外部の健全な批判が届かない閉鎖社会であるからこそ、こうした愚行がいつまでも続くのであろう。
(第1465回に続く)
【プロフィール】
井沢元彦(いざわ・もとひこ)/作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。
※週刊ポスト2025年9月12日号