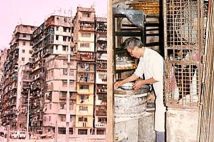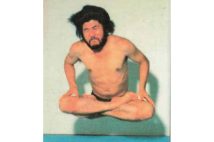ちなみに、罪つまりケガレに満ちた人々を収容する牢屋の奉行、つまり牢奉行は奉行職であるので一応旗本であったが、転任や昇進もある他の奉行職と違って、石出帯刀(世襲名)という人物が代々務める習わしであった。これも一種の差別であることはおわかりだろう。
「不浄役人」という言葉を解説するだけでこれだけ日本史の特徴を紹介することができる。逆に言えば、「言葉狩り」をしてこうした言葉を消してしまえば、それに伴ってこうした事実も消されてしまうのである。だから、「大東亜戦争」を「アジア・太平洋戦争」と言い換えたり、「唐入り」を「朝鮮侵略」などと言い換えたりしてはならないし、ましてや「不浄役人」のような言葉を「狩」ってはならないのだ。それでは歴史の真実を隠蔽することになるからだ。
念のためだが、私は豊臣秀吉の「唐入り」は朝鮮侵略では無い、と主張しているわけでは無い。分析の段階でそう認定するのは自由だが、当時使用された言葉を「言葉狩り」するな、と言っているのである。いわゆる「唐入り」つまり文禄の役、慶長の役について私見を述べれば、文禄の役は「日明戦争」であり、慶長の役は「朝鮮侵略」だろう。
だが、かつて左翼歴史学者全盛だった日本では、GHQが「大東亜戦争」に代わって「太平洋戦争」を定着させてしまったように、一つの歴史用語が「言葉狩り」によって消されてしまった。それは「帰化人」という言葉である。帰化人とは日本の黎明期に中国や朝鮮半島からやってきて日本に帰化し、日本の政治や文化の向上に貢献した人たちである。だから、半世紀ぐらいまでは普通に歴史用語として使われていた。百科事典にも次のようにある。
〈帰化人 きかじん
古代に海外から渡来して日本に住みついた人々、およびその子孫。平安時代以降もたえず少数の来住者があり、また近代には外国人が日本の国籍を取得することを法律上やはり帰化といっているが、来住者の数が多く、しかもそれが社会・文化の発展のうえでとくに大きな意味をもったのは、平安時代初頭までだったので、日本史上で帰化人といえば、主としてそのころまでの人々を指すのが普通である。(以下略)〉
(『世界大百科事典』平凡社刊 項目執筆者関晃)
「帰化」という言葉は現代も同じ意味で使われており、当然ながら差別的な意味はまったく無い。にもかかわらず左翼歴史学者たちは、これを「渡来人」と言い換えるべきだと主張したのである。