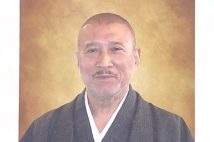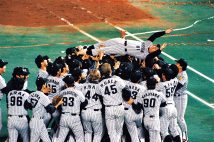第24回大会でタケノコメバルなどの放流をされた天皇皇后両陛下(当時。写真は2014年10月、香川県高松市。撮影/雑誌協会代表取材)
天皇家と大会のかかわりは、1950年代に遡る。当時は、戦後の経済発展とともに海浜の埋め立てや開発が進み、有害物質や汚染排水で漁場が荒廃していた。さらに、国内需要の急増で乱獲が生じ、水産資源の悪化が進んでいた。
この状況を解消すべく、1950年代半ばから、水産資源保護の重要性を訴えるため、「放魚祭」という行事が開催されてきた。その第2回に、当時皇太子であられた上皇陛下がご臨席されていた。これが、豊かな海づくり大会の前身となる。
「1980年、当時の全漁連会長が東宮御所にお伺いする機会があり、両殿下に『かつての放魚祭を充実させ、皇室のご理解のもと国民的行事として毎年開催し、豊かな海づくりを世論に訴えて参りたい』とお話を申し上げたところ、ご理解をいただくことができたそうです。
その後、宮内庁や水産庁などが協議して、全国規模で毎年開催される『全国豊かな海づくり大会』に両殿下のご臨席を承る方向が示されました。つまり、この大会は、上皇上皇后両陛下のご理解から始まったのです」(大森専務)
早朝から胴長姿でハゼを捕獲された
御用邸のある神奈川・葉山や静岡・沼津の海で、幼少期から魚に親しまれた上皇陛下は、魚類研究をライフワークにされ、退位後も皇居内の生物学研究所で研究を続けられている。特にご専門のハゼの分類では世界的な権威であり、今年6月にも新種のハゼ2種類を発見し、論文を発表された。
北海道のサロマ湖で開催された第5回大会(1985年)では、そのハゼをめぐるハプニングが起きた。
「大会翌日の早朝に、殿下自ら胴長姿になられ、サロマ湖に生息するハゼを捕獲するために湖に入られたのです。研究のみならず資源の維持に対する思し召しを感じました。
天皇陛下になられるお方が胴長姿で湖に入られることには驚きましたが、大会を活用していただいたことをうれしく思いました」(大森専務)
よほど印象深くあられたのか、翌1986年の歌会始で、美智子さまはこうお歌を詠まれた。
《砂州越えてオホーツクの海望みたり佐呂間の水に稚魚を放ちて》
広島県で開催された第9回大会(1989年)は、「陛下が海づくり大会に継続してご臨席されるのか注目されていた」(皇室記者)という。
「昭和から平成へと元号が変わり、上皇陛下は皇太子さまから天皇になられた。お立場が変わられたことで、皇太子さまに引き継がれるのではないかという見方もありました」(前出・皇室記者)
大森専務が当時を振り返る。
「当時の全漁連会長が侍従次長にお伺いを申し上げたところ、『そのことについては何も心配なさらないで結構です。海づくり大会はお上がご自身で持ちあがると仰せられております』とお話をいただいたそうです。会長は『感極まったことは忘れられない』と申しておりました」